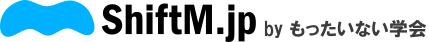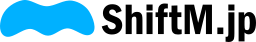宣言:巨大震災後の日本「自然と共存の国つくり」
A.3.11東日本大震災の教訓
3.11東日本大震災は、沿岸低地は壊滅的な津波災害、福島第一原発はレベル7の放射能災害で、未曾有の大惨事になった。約28,000人の生命と莫大な国民の資産の喪失、国土の劣化、国力と信頼の低下を招いた。復興には社会の自然との関わり方から正すべきである。
【教訓1:支配から共存へ:自然観のマインドシフトを】
人為が招く大災害は、その社会の最大の浪費である。その大災害が、なぜ繰り返されたのか。安全が謳い文句の原発が、なぜチェルノブイリに次ぐ大惨事を起こしたのか。それらの根本的理由は、「技術で自然の猛威を制することができる」という自然支配観にある。自然支配観は、経済的効率を優先するがゆえに自然の摂理を、傲慢に無視することになる。技術神話、安全神話が形成され、技術も安全も、かえって蔑ろにされた。
「自然では人知を超えたものが起こりうる」、「自然は知り尽くせない」が、まともな自然観である。だから、古来より、自然を畏敬する心、自然と共存社会のかたちが作られてきた。自然支配観から自然共存観へのマインドシフトが必要である。
【教訓2:石油依存型マインドでの復興は許されない】
1933年の三陸地震津波以来、安価な石炭・石油の高エネルギーで、防災人工物が造られた。しかし、78年後の東北地方太平洋沖大地震は、それを簡単に破壊した。同規模の大地震大津波は何度も繰り返されよう。次は何十年先であろうか、安価な石油・化石燃料が減耗して使えない時代になる。もし自然と対峙するような復興計画なら、それは資源不足で中断されるか、文明の廃墟になろう。石油依存型マインド踏襲での復興は許されない。
東北地方太平洋側に限らず、日本の永続的な国つくりは、「自然と共存」しかない。
B.石油文明社会の次は自然共存のGDH低エネルギー社会
【石油ピークで石油文明は終焉へ】
文明のかたちは、主たる動力エネルギーによって決まる。自噴する石油のEPR(エネルギーの生産利得倍率)は100に及び、生産と輸送の卓抜な動力として地球をひとつの現代文明圏とした。また便利な化学原料であり、日本1.3億人、世界70億人の人口収容を可能にした。その石油は2006年に生産ピークに至り、価格高騰のトレンドにある。2013年には石油生産減耗に入る。石炭ピークも間近で、2020年頃には安い天然ガスもピークになる。
化石燃料のEPRはすべて10以下に低落し、現代文明を駆動する動力が急速に失われている。オイルサンド、シェールガス、メタンハイドレートはEPRが非常に低く、その採掘に深刻な地球破壊を伴う物質であって、もとより石油文明のエネルギー資源ではない。
【原子力発電も自然エネルギーも石油代替でない】
石油文明の利便を原発で延命しようとの考えがある。しかし良質ウランの生産ピークは遠くない。原発はウラン開発から建設、最終処分に至るまで、化石燃料に依存する。化石燃料が使えない時代になると、廃炉作業、最終処分場建設もできなく野ざらしになる。放射性物質は生体に最も危険な物質である。その放射能を放散するレベル7の大事故が、大津波災害と同程度の頻度で起こっている。却って文明的危機を加速する。
原発に替って自然エネルギーによる石油文明延命の考えがある。自然エネルギーは、濃集密度が低くて自然任せのためEPRが低い。自ずから石油文明延命のエネルギーでない。
従って、石油文明を延命できるような動力エネルギーはない。エネルギー浪費型の石油文明とは潔く決別し、自然エネルギー中心の地産地消型低エネルギー社会へ転換しかない。
【経済活動が縮小するが、豊かな自然共存社会を】
社会のエネルギー消費量が低減すると、一般的に社会の経済活動が縮小するが、国民生活の内容が低下するとは限らない。日本より一人当たりの経済規模の小さい国で、日本より生活内容の高い国は幾らでもある。経済規模の指標GDPを開発したS.クズネッツは「GDPは国の経済の善し悪しを測る指標としては適さない」と断言し、故ロバートケネディは「GNPには中毒物質、交通事故、犯罪、環境汚染、環境破壊、戦争兵器や武器などが含まれるのに、健康、教育の質、楽しさ、美しさ、知恵、勇気、誠実さ、慈悲深さなど・・・・「生きがい」につながるものがすっぽり抜け落ちている」と指摘した。GDPに含まれる「悪のマネーフロー」を取り除き、含まれていない「生きがいにつながるもの」をGDH(国内総幸福度)として評価することが、自然共存低エネルギー社会のマインドセットである。先ず1960年代の頃の生活をイメージすると、電力消費量は現在の3分の1だが、省エネ型のテレビ、洗濯機、冷蔵庫、エアコンあるが、自動車を極力使わない生活である。ただし石油ピーク・脱原発のこれからの日本に、エネルギー多消費産業は向かない。
C. 自然共存・低エネルギー社会のかたち
自然共存・低エネルギー社会の特徴は次のように表現できよう。
① エネルギーや資源の浪費のない社会、モノ・コトを大切にする社会。
② 自然と共存して、自然変動に対して柔軟な社会。従って、地球の気候変動が
温暖になろうが、寒冷になろうが、永続できる社会。
② 自然と共存して、自然変動に対して柔軟な社会。従って、地球の気候変動が
温暖になろうが、寒冷になろうが、永続できる社会。
③ GDHがコミュニティのモノサシである社会。
自然共存社会では、地産地消型コミュニティが基本的なユニットの社会である。日本は海に囲まれ、山多く、太陽、水、土の多様な幸に恵まれた国である。一方、地震、火山、台風が頻繁で弱い地盤の怖い国である。自然を畏敬するマインドで、地域の自然を良く理解することが前提である。
【地域区分けの基本形】 自然エネルギーには、風力、太陽光(熱)、バイオマス、小水力、地下水、熱水(温泉等)、地中熱など多くのタイプがあり、地域によって様々な特徴ある形で存在している。山から海に向かって河川流域で地域を区切ると、いくつもの自然エネルギーを工夫して組み合せて使用できる。山地と扇状地、平地、前浜を結ぶ河川流域は、陸水の循環と動植物の栄養源循環が保持できうるバイオリージョンの基本形である。
【自然共存コミュニティの基本的なコンセプト】 地域コミュニティは、農林業集落とコンパクトシティからなる。自助・共助・公助が機能する安心のコミュニティをつくる。災害に強い安全なコミュニティをつくる。コミュニティの維持に必要なエネルギー、食料自給を、コミュニティ自身で議論し工夫する。働き甲斐ある文化的なコミュニティをつくる。
【災害に強い地域つくり】 自然の猛威に逆らわない河川や海岸の復元と利用、集落立地の改善を行う。河川を直線状・三面張りしても自然には破壊する力がある。武田信玄は洪水と共存のために「霞堤」を考案し、流域を災害から守り、かつ耕地を肥沃にした。大津波が襲来する沿岸低地は、安全な住民生活、商工業の場でない。自然保護地区とし、鳥獣生態が豊かになると、津波の来ない高台の居住地、田畑の生態も豊かになる。
【地域自給を実現する農林業】 田畑につながる山の斜面で立体農業を展開する。田畑の農耕に穀樹栽培、林間牧畜、川魚養殖を加えて、多彩な食料自給が実現できる。さらに余剰食料、農家加工品をコミュニティに供給して現金収入が得られる。山や田畑の栄養分は、堆肥と牧畜・鳥類の糞尿などによって生態循環的に供給できる。石油系肥料は不要である。
【コミュニティと交通】 コンパクトシティには行政機関、地域産業事業所、市場、教育施設、医療施設など、コミュニティの都市機能を有する。農林業集落とコンパクトシティの間の主な交通は、地域巡回バス、自転車、徒歩である。他地域のコンパクトシティとの主な交通手段は、鉄道とバスである。電気自動車もEPRが低く、極力使わない。
【GDHのネットワーク】 食料自給と労働の分かち合い、そして信頼の絆が、コミュニティの構成員の幸せ感のモノサシ、GDHの前提である。コミュニティが、自然と共存してGDHを進めていけば、多くの人々がリターンし、参集するだろう。なぜなら、GDHはGDPより、はるかに優れているから。コミュニティは、高齢化などによって増加している買物、医療、情報などの「弱者」に対して、とりわけ共助・公助を充実させる。民主主義的な自由と平等、教育文化、医療福祉の公助を充実させる。
石油文明の終焉はすでに始まっている。3.11大惨事を引き起こした民族的な屈辱からの永続的な復興は「自然と共存の国つくり」である。時間的余裕はそんなにない。