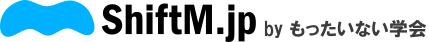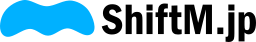そろそろ「42年分!」的な議論をやめよう
また「42年分?」と嘆く前に
BP社が発行する2009年版の統計年鑑(BP Statistical Review of World Energy 2009、6ページ)によると、世界には枯渇までに42年分の石油が残っているというデータが掲載されている。
「42年分?以前にも同じような数字を聞いたことがある。それから何年も経つのに減っていないではないか。技術の進歩の結果だろう。石油について当面は心配する必要はない」といった声が聞こえてきそうである。
数字自体は信頼できるデータに基づいている。ただし、この種の数字はエネルギー問題を考える上ではあまり役に立たない。枯渇までの年数に関しては、その時点での可採埋蔵量(R)をその年の生産量(P)で単純に割り算するというR/Pが指標として使われている。42年という数字はその結果である。
しかしながら、この指標はその年の時点での「静的」な状況を表しているに過ぎず、技術革新によって将来的に可採埋蔵量が増加することや、時間軸に沿って生産量が増減する「動的」な変化を捉えることができないことから、将来予測の指標として十分なものではない。
わかっている国は、政府は、わかっている!
石油業界が相変わらず楽観的な見通しを発表し続けている中、感度の高い政府機関の中には「石油ピーク論」を真剣に捉え、目前に迫りつつある危機に備えようとする動きも見られるようになってきた。
たとえば、2010年3月22日には、イギリスのエネルギー・気候変動大臣が石油ピークに対する政府の対応を話し合うための会議に出席している。この会議は、参加者はここで得た情報を自由に利用可能だが、発言者の特定をしてはならないという、いわゆる「チャタム・ハウス・ルール」(Chatham House Rules)のもとで行われたため、エネルギー・気候変動大臣の石油ピークに対する認識を知ることはできない。しかしながら、イギリスの『ガーディアン』紙は、こうした会議に大臣が出席したこと自体が「政府の重要な政策転換」であると報じている。
同様に、アメリカ軍は、統合戦力軍(US Joint Forces Command)による報告書『統合作戦環境報告』(The Joint Operating Environment Report 2010、29ページ)の中で、「2012年までに石油生産の余剰能力は全くなくなり、2015年には日産1000万バレルの供給不足に陥るだろう」とするエネルギー展望を示している。
アメリカ政府はエネルギー省を中心に極めて楽観的な石油の将来予測を示し続けているが、石油の動向が組織にとって死活的な問題を与えるアメリカ軍は「石油ピーク論」を認める形で極めて現実的な認識を有していることが読み取れる。
つまり、「知っているところは知っている」のであり「わかっているところはわかっている」ということである。楽観的な「公式見解」と別のところでは、すでに現実的な対応が検討されている。これが国際社会である。いつまでも「公式見解」に拘泥していると、いつの間にか取り残されてしまう可能性がある。
日本も、そろそろ「目を覚ます」時ではないか?
日本では、相変わらず「42年分!」的な議論が幅をきかせている(ように思う)。問題は、「枯渇」(running out)ではない。供給ピークの後に訪れる「減耗」(depletion)であり、そのことによる需要と供給との「乖離」である。
R/P指標の世界に決別し、EPR(Energy Profit Ratio)を軸としたエネルギー論を展開すべき時期にさしかかっている。残された時間はそれほど多くない。なにしろ、エネルギー・シフトには恐ろしく長い時間を要するのである。今、目を覚まさなくては、いつ目を覚ますのであろうか?