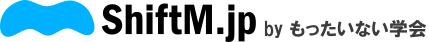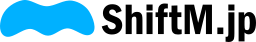石油減耗時代の雇用と当為
「ブラック企業」という言葉をしばしば耳にするようになった。不当解雇やサービス残業など、労働基準法をはじめとする労働法に抵触する職場が増えているようなのだ。20世紀には労働者を守るべく法制的な整備を行ってきたわけだが、不面目ながら近年、そのような法令をとても遵守することができない職場が増加しているわけである。
ブラック企業の中には、守銭奴と化した経営陣とドレイのような従業員という構図の悪質な会社もあるかもしれないが、むしろ世界経済の変調に伴う経営の悪化ゆえにやむを得ず法を侵すことを余儀なくされている職場も少なくないのではないか。名を馳せた大企業でさえも経営再建のために早期希望退職者を募らざるをえない状況が珍しくなくなっている御時世なのだから。
さて、目下の世界経済の変調は石油減耗に端を発する人類史的転換点を迎えたことに由来するのだから、ブラック企業の増加を経営陣の不徳だの新自由主義への傾倒だのに帰して悲憤慷慨しても救われないだろう。労働基準法は遵守すべきであるが、世界的なエネルギー制約ゆえに収益が伸びない状況では賃金として報いることがどうしても困難になることを推察しなければならない。ブラック企業の問題は、石油文明の翳りを映した症状であり、低エネルギー社会を展望する上で無視できない問題だろう。
再生可能エネルギー技術を基盤とした低エネルギー社会への移行を雇用創出(純増)の機会と捉える声も聞こえてくるが、それは本当だろうか。たしかに低エネルギー社会ともなれば、それまで機械を使って済ませていた諸々のことを、自身の筋力を頼りにして、遣り遂げなければならなくなるだろう。いろいろとやるべきことは増えそうだ。だが、それは賃金を伴う雇用の機会を増やすという話ではないだろう。賃金が支払われるには付加価値を生むプロセスが前提されねばならないが、付加価値の総額はエネルギー供給量に比例するのだ。(註:『おいそれと帰農できない理由について』を参照されたし)しかるに、インフレ策が採用されるでもない限り、利用可能なエネルギーの供給量の減少と共に支払い可能な賃金の総額もまた減少すると考えられ、最低賃金の引き下げなしには雇用純増は望めないということになる。仮にインフレ策が奏功して雇用が守られたとしても、はたらけどはたらけど猶わが生活楽にならざり、という古い詩句をしみじみと味わうことになるばかりだろう。
それでもドイツでは再生可能エネルギーで38万人もの雇用が創出されたという話を引き合いに出す向きもあるが、それはピークオイル前に着手して達成された話である。ピークオイル前には、EPRの大きな石油で補填するかのようにして、EPRは小さくとも将来に備えるためのエネルギー開発事業を展開することができた。日本でも昔はサンシャイン計画や冗談のような名称のムーンライト計画なる営みに取り組んできたわけであり、新エネルギー技術に関連した雇用は生み出されていた。だが、既にピークオイルを過ぎたと言われる。今ではドイツの太陽光発電ビジネスの綻びを伝えるニュースも届けられるようになっており、wishful thinkingには自戒を呼びかけたい。
そもそも、今は昔、高度経済成長以前の日本の低エネルギー社会には、「農家の次三男問題」と呼ばれた未就業問題があった。さらに、戦後のベビーブームの時代に誕生した若者の労働市場参入に備えて雇用を創出できなければ、社会不安を呼び起こすかもしれないという切実な政治課題もあった。その問題を解消したのがエネルギー消費の拡大を伴った高度経済成長だった。
今ではほとんどの日本人が「国民所得倍増計画」の理論的支柱であった下村治の名前も知らず、曲がり形にも豊かさを享受できた要諦を顧みようともしないで、経済成長の夢や労働問題を語り合っている。下村は、「与えられた条件が許すかぎり、できるだけ積極的、能動的に創意工夫を重ねて、可能性の開拓に努力すべきだという立場」(『ゼロ成長脱出の条件』)から、「経済活動はその国の国民が生きて行くためにある。国民の生活をいかに向上させるか、雇用をいかに高めるか、したがって、付加価値生産性の高い就業機会をいかにしてつくるか、ということが経済の基本でなければならない」(『日本は悪くない』)という国民経済の視点に立って、経済成長の処方箋を練り上げて、それを実現させた国士だった。だが、下村はおめでたい成長論者ではなく、リアリストであり、1970年代のオイルショックの後にはゼロ成長論者に転じ、1987年に記された彼の遺作には「今後の成長のペースは、現在のエネルギー供給の限界、現在の資源供給の限界で頭を押さえられる」と明記していた。そして、私たちはエネルギー制約を正視しなければならなくなった。
ところで、下村治は経済成長という難題に立ち向かうにあたり、次のような気概を示した文章を残している。 「われわれは、アーノルド・トインビーの歴史観を思い出す必要がある。文明の生成、発展、崩壊の過程を決定する基本的な要因は、その文明に対する挑戦とこれに対する応答であるという原則である。経済の成長問題も、このような歴史の一つの側面であろう。われわれが、民族の成長と発展とをめざして、歴史的な努力を重ねる過程において、いかなる問題をみずからの問題としてとりあげるか、いかにして、このような課題に対する解決の努力を推進するか、これがわれわれの運命を決定することになるわけであるが、経済の成長はこのような歴史的な営みにおける、一つの重要な側面にほかならない。」(『経済大国日本の選択』)
そのトインビーの大著『歴史の研究』によれば、過去の文明社会において、社会の衰退という破局によって安楽な道が無慈悲にとざされたとき、「復古主義」、「未来主義」、「超脱」、「変貌」という四通りの生活態度が姿を現すという。このうち、過去の成功体験を懐かしむ「復古主義」、前提を無視した想像の未来を描く「未来主義」、彼岸的逃亡と言うべき「超脱」の三つは行き止まりの袋小路であり、「変貌」と呼ばれる実行可能な生き方を探求する能動的な営みだけが次なる文明社会の構築を可能にさせる芽を残してきたそうだ。私たちは下村治の時代とは条件が異なる文明の課題に直面しているわけだが、トインビーの歴史観に照らすならば、然るべき「変貌」を遂げないことには、死滅さえも杞憂ではないということなのだろう。
そこで、「変貌」を遂げる上で参考となりそうな記事を紹介したい。Richard Heinbergはじめ石油減耗問題に警鐘を鳴らすカッサンドラ達が未来について語った “Facing the New Reality: Preparing Poor America for Harder Times Ahead” と題するレポートの中で、Dmitry Orlov氏が「雇用」について記しているのだ。彼の主張は、エネルギー・資源の減耗を慮るならば、雇用創出自体がいわば「もったいない」精神に悖る行為であり、雇用すなわち賃労働jobはなくなる趨勢にあっても、必要ゆえに働くことworkはいつまでも続く、そして、必要な営みを支え合う仕組みとして贈与経済の再考にヒントが見出せるのでは、というものだ。以下は、その訳である。
雇用 / ディミトリー・オルロフ
政治家がマイクの前に現れると、あなたはやがて「雇用job」という言葉を何度も耳にすることになるだろう。雇用創出、雇用創出のための中小企業支援、職業訓練、雇用、雇用、雇用。
だが、注意深い分析結果は2008年の金融危機以来、雇用創出に関連した政府支出は、国内総生産よりも国家債務の増加にますます寄与している。
雇用創出はあまりにも弱々しいもので、(米国の)人口増加ペースに対応できず、社会の福利増進を期待することはできない。それどころか、今となっては、経済活動において雇用を生み出すことは、減耗中にある資源の基盤を圧迫することに加担することになるわけで、エネルギー、商品、食糧の価格を記録的な水準にまで高騰させ、数世代にわたり賃金が停滞し続けている人々をさらに圧迫することになるだろう。
さらに言えば、創出されたわずかな雇用はたいていサービス部門の雇用であり、その一方で製造業部門の雇用は空洞化し続けている。経済理論はサービス部門の雇用が製造業部門同様に価値を生むとしているが、サービス部門の雇用は実のところ債務を創出するばかりで、製造業と輸出に支えられた経済国に莫大な黒字を溜め込ませることになる。(註:下村治は『ゼロ成長脱出の条件』にて「われわれの消費生活は財貨だけでなくはなくて、サービスも含んでいる。財とサービスとを結合することによってわれわれは生活を営んでいるが、サービス部門においては、財の部門におけるような生産性向上はない。」と断言していた。)
それでも人々は必需品を手に入れるためにマネーを欲するわけで、マネーを得る合法的な方法は職に就くか生活保護を受けるかだ。
さて、うんざりするほどの旧態依然の「雇用、雇用、雇用」の大騒ぎは有害無益だが、雇用なしで済ますとするならば、人々はどうやって必需品を手に入れることができるだろうか?単純明快な答えは、働くことworkである。賃労働jobはなくなるかもしれないが、常にやらねばならないことworkはある。就業していない人々に彼らのコミュニティを手助けするような好ましい営みに就かせ、次いで、人々を手助けできるようにすることこそが課題なのだ。
この課題に対する解は、自由市場イデオロギー以後を見通すことが出来ない者には思い浮かばないだろう。だが、主要な資源が乏しくなると、要するに今の私たちの置かれた状況では、やがて市場が崩壊することが予期される。このような時代には、市場は買い溜めや投機による不当利得といったひどく有害な特徴を顕在化させて、しばしば政府が介入して配給制を実施することになる。
だが、市場システムよりも数千年先行して存在していた社会制度、物のない時代にはるかに強力な回復力を例証している社会制度のおかげで、市場が出来る前から生活はあったわけだし、市場がなくなってからも生活は続くことだろう。
もっとも重要な営みは、ポトラッチ(註:マルセル・モース『贈与論』を参照されたし)を中心とした贈与経済であり、そこでは諸個人の格は、彼や彼女が何を持っているかではなく、どれだけ多くの贈り物を渡せるか、で評価される。
互恵的な贈与を通しての相互扶助は世界中のコミュニティにおいて長い間存在した。贈与は物々交換を補完することができ、地域通貨システムの中で発展することさえ可能であり、互いの親切な行為の遣り取りの蓄えについての金融的表現にもなる。
うまく事を運ぶためには、このような活動は贈与や相互扶助といった現存する文化的営みの上に構築されねばならないだろう。キリスト教やイスラム教、その他の宗教に見られる義捐活動や慈善活動といた宗教的に是認された営みは、商業的ではない活動へと拡張され得るだろう。そして、商品市場に基礎を置いた人間関係への依存を減らしていけば、ますます多くの人々が雇用されることなく生き残ることが可能になるだろう。