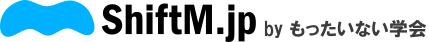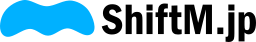化石燃料の枯渇と世界と日本の食料問題
東京工業大学 名誉教授 久保田 宏
日本技術士会中部本部・副本部長 平田 賢太郎
人類の歴史のなかで、世界の人口を支配してきたのは食料ではなかろうか?化石燃料を成長のエネルギー源とすることができるようになった産業革命によって、急激に増加するようになった世界人口を養うことができているのも、化石燃料をエネルギー源として造られる化学肥料の御蔭である。しかし、この化石燃料が枯渇すれば、増え続ける世界の人口を支える食料供給の限界が来る。この限界を克服するために、食品廃棄物等から造られたコンポストの農地還元による持続可能な農業生産体制をつくるとともに、各国の食料供給の不均衡をもたらしている貧富の格差を是正する国際平和を再構築すべきである。このような、世界の食糧問題の解決の基本となるのが、各国が食料を自給できる人口当たりの農地面積の確保である。人口、3千万以上の国家で、この条件を満たすことのできない国は、日本と韓国ぐらいである。食料だけでなく化石燃料のほぼ全てを輸入に頼らなければならない日本では、国際平和を追求するなかでの自由貿易によって必要な最小限の食料を輸入に頼る以外にない。同時に、化石燃料枯渇後の持続可能な有機農業のモデルを世界に先駆けて創るべきである。
化石燃料が使える間、食料の供給が世界の人口を制約することはないであろう
人類が農耕を始めてから産業革命以前までの世界人口は、自然淘汰の原則で制御されていたのではなかろうか。人類の生存のために基本的に必要な食料は、主として農作物として与えられたが、凶作時に備えた備蓄は十分でなかったであろうから、食料供給が人口を制御する大きな因子になっていたと考えられる。
産業革命以降の人口の急増は、衛生状態の改善での疫病による大量死の減少と考えられている。一方で、産業革命発祥の地、欧州で増え続けるようになった人口を食べさせるための農地面積の拡大は、植民地の拡大と新大陸(アメリカ)への移民政策で賄われた。また、食料としての農作物の生産性(単位農地面積当たりの農作物の生産量、反収)を増加するために、三圃農業による生産方式から化学肥料に依存する方式への転換が行われたが、この化学肥料のなかの窒素肥料(その主体のチリ硝石)の枯渇が、19世紀末の西欧の大きな関心事となった。
この問題の解決に大きく貢献したのが、ハーバー・ボッシュ法による空中窒素の固定によるアンモニア合成の工業化(1913年)の成功であった(文献 1 参照)。
このアンモニア合成反応の窒素の相手の水素は、水力電気による水電解法から、化石燃料の石炭、石油へと変遷し、現在は、天然ガスを原料とすることで、最も安価につくられている。この窒素肥料の施用により、単位耕地面積当たり農作物(西洋での小麦)の収穫量が飛躍的に増加した。世界的には、まだ農地面積の拡大の余地が残っており、化石燃料を使って窒素肥料を増産できる間は、食料生産量が世界人口を制約することはないと考えてよさそうである(文献 2 参照)。
このような状況のなかで、ごく最近、人為的に食料危機をつくりだしたのが、農作物の輸出大国、米国が輸出価格をつりあげるために飼料作物のとうもろこしを利用したバイオ燃料の生産である。これが世界の一部地域における天候不順による農作物の減産と重なり、一時的な食料供給の不足をつくりだし、過大に報道された(2008年)。実際に被害を受けたのは食料を輸入に頼らなければならない一部の貧困国であった。
やがて、「世界の食料危機がやってくる」と言われたもう一つの理由として、食品の質の向上の問題がある。世界中の人がアメリカと同じように肉食、特に牛肉を食べるようになれば、世界の食料不足の問題が深刻になるとされている。しかし、人間の嗜好は、宗教上の制約も含めて、そう簡単には変わることはないから、さほど心配する必要はなさそうである(文献2参照)。
飢餓の問題は、国際平和の回復とグローバル化による配分の問題で解決できる、
上記したように、化石燃料がある限り、世界全体でみれば、当面は、食料の供給は何とかなりそうである。しかし、それには、幾つかの条件がつく。
その第一は、配分の問題である。世界全体では自給可能でも、国別には、その供給に大きな不均衡がある、食料の主体である農作物の自給のために必要な人口3千万程度以上の世界のいくつかの国および地域の単位人口当たりの農地面積の値(国および地域ごとの農地面積の値を、それぞれの国および地域の人口で割って求めた)Apを表1に示した。
表1 世界各国および地域の単位人口当たりの農地面積( Ap =(農地面積)/ (人口)、単位:ha/人。括弧内数値は国および地域別のApを世界のApで割った値)(川島博之の著書(文献2)に記載のFAO(国際食糧農業機構)のデータをもとに計算した)
日本 韓国 中国 タイ インドネシア インド イギリス フランス ドイツ イタリア スペイン
0.0369 0.0386 0,117 0,275 0.154 0.154 0,146 0.323 0.146 0.184 0.389
(0.154) (0.152) (0.490) (1.15) (0.646) (0.644) (0.610) (1.35) (0.609) (0.970) (1.63)
ロシア ウクライナ イラン サウジアラビア カナダ アメリカ メキシコ ブラジル アルゼンチン オーストラリア ニュージランド 0.869 0.716 0.263 0.1545 1.62 0.589 0.262 0.357 0.745 2,38 0.835
(3.63) (2.99) (1.10) (0.646) (6.78) (2.46) (1.10) (1.49) (3.12) (9.95) (3.49)
北アフリカ 東アフリカ 西アフリカ 中央アフリカ 南アフリカ 北朝鮮 世界 西洋 東洋
0.182 0.212 0.316 0.225 0.274 0.0893 0.239 0.532 0.142
(0.758) (0.884) (1.32) (0.936) (1.14) (0.372) (2.23) (0.594)
この表1の各国の単位人口当たりの農地面積Ap の値は、各国の人口当たりの農作物の生産可能量を表わしている。したがって、世界全体では、このApの値で、世界人口に対する食料が供給できていると仮定すると、この各国および地域のApの値を世界のApの値(0.239 ha/人)で割った括弧内の数値は、国および地域別の食料の自給率の値にほぼ比例する値と見ることができる。
ただし、表1に示した西洋と東洋のApの値には大きな違いがある。これは、両者間の食生活様式と農業生産方式の違いによるものである。すなわち、西洋では、肉(特に牛肉)食が多いため、家畜用の飼料穀物の生産に広い農地面積が必要になる。さらに、東洋では主食の米の生産用の水田での生産効率(単位農地面積当たりの生産量、すなわち反収) が西洋の主食の小麦のそれに較べて大きく、結果として、両者間のApの値に3.75 ( = 0.532 / 0.144) 倍もの大きな違いが生じている。
したがって、この括弧内の数値から直接、各国および地域の食料自給率の値を求めることはできないが、大凡の比較を表していると見て、この括弧内の数値を各国の食料自給可能特性値とでも呼ぶことにする。
ところで、この各国別の食料自給可能特性値であるが、ここに示していないシンガポールなどの都市国家を除いては、この値が極端に低い国が、日本と韓国以外には見られないことに注意する必要がある。これは、世界のほとんどの国が、人間の生命維持に必要な食料としての農作物の最低限の自給がほぼ可能になるように努力している結果と見てよいのではなかろうか。
いま、飢餓が問題になっているアフリカでも、表1に示す 北、東、西、中央、南の各地域別の自給可能特性値の値は、全て、1に近い値を示している。すなわち、これらアフリカにおける飢餓は、かつての欧州列強による植民地から解放されたこれらの国内における人種間の軍事紛争の影響による地域的な食料供給の不均衡によって生じたものとみてよい。
いずれにしろ、下記に、日本の食料問題として示すように、日本と韓国の食料自給可能特性値の異常に小さい値を含めて、当面の世界の食糧問題は、自由貿易による、いわゆるグローバル化による配分の問題さえ解決できれば、大きな問題にはならないであろう。
化石燃料枯渇後の世界の食料問題の抜本的な解決のためには持続可能な有機農業の普及が求められなければならない
やがてやって来る化石燃料枯渇後の世界の食糧問題を抜本的に解決するためには、化石燃料エネルギーを必要としない持続可能な農業生産方式の確立が求められなければならない。
上記したように、世界人口の増大に見合う農作物の生産性(反収)の増加をもたらしたのは、化石燃料をエネルギー源として窒素肥料(アンモニア)の生産である。やがてやって来る化石燃料枯渇後の世界でも、このアンモニアは、自然エネルギー(再エネ)電力による水の電気分解により造られる水素を利用すれば、多少高くついても何とか造ることができる。
化石燃料の枯渇後に問題になるのは、農業生産に必要な化学肥料のチッソ以外の成分、リン酸およびカリ肥料の供給である。すでに、リン酸肥料用の資源の供給で、その枯渇が問題になってきている。
一方で、現代文明生活のなかで、厨芥などの大量の食品廃棄物や下水汚泥、さらには、蓄糞尿や、農作物遺体などの農作物起源の有機系廃棄物が大量に排出されている。これらの全てを、生物的に安定な(腐敗しない)形に、すなわち、コンポスト化して農地還元し、農作物を生産する有機農業を基本とする循環社会システムが創られるべきことが、古くから一部の識者の間で主張されてきた。
具体的には、農業生産において、人為的な合成化学肥料や、農薬等の一切を排除するとの宗教的な信念に支えられた有機農業の実践であるが、それが、石油危機の後、有限の化石燃料に依存する化学肥料と機械力に頼る現代農業に代わって、安心・安全な食品としての農作物を生産できる持続可能な農業生産方式として、見直されるべきであることを、私どもは30年以上も前から主張続けてきた(文献1参照)。
この有機農業では、肥料の3要素の窒素、リン酸、カリの他、農作物の生育に必要なミネラル分も農地還元される。さらに大事なことは、農地の保全にとって基本的に必要な有機質成分(炭素)の農地土壌中への供給による土質の再生・改良効果が図れることである。農地における、この土壌の再生・改良がなければ、持続可能な農業生産は可能とならない。すなわち、このような循環社会システムを完成することで、初めて、持続可能な農業生産が可能となり、人類の究極的な生存のための世界の食料問題の解決が可能となる。
この有機農業の普及は、先ず、現在、高価になりつつある化学肥料の購入に苦労している途上国から始め、徐々に、先進国に広めるべきである。
戦後の日本の食料問題は、安い化石燃料に支えられた貿易黒字で輸入できた食料で解決されてきた
食料自給率 100 % を実現するための日本の人口を問題にするとき出てくるのが、江戸時代の人口であろう。約300年もの間、人口が約3,000万人とほぼ一定に保たれていたのは、当時の貨幣価値が、年貢米の形で主食の米に換算されていたから、地方分権を任されていた各藩が、自藩内の食料が自給できるような人口抑制政策を採らざるをえなかったためではないかと考えられる。
この軛を断ち切ったのが、明治維新による中央集権政治である。産業革命後の西欧文明の導入により、急激に増加し始めた人口のはけ口を求めて、日韓併合、また、中国への侵略による食料の自給のための軍事力の行使から、さらには、軍事力保持に必要なエネルギー資源(石油)の確保のために、ナチスドイツが始めた第2次大戦に捲き込まれてしまった。
いま、食料需給との関連で日本の人口問題を考えるとき、このような歴史的な事実を厳しく認識することが先ず必要である。
食料の供給先の植民地を失った敗戦後の日本が、一時、米国からの食料の無償援助に頼らざるを得ない時期があったが、やがて、安価に輸入できるエネルギー資源としての中東の石油と、明治維新後の教育制度に支えられた科学技術力を使って輸出産業を振興させ、つい最近、中国に追い抜かれるまで米国に次ぐ世界第2の経済大国として、増加する貿易黒字を使って、自給に頼らないで食料問題を解決してきた。
それが、いま、中国をはじめとする発展途上国の急激な成長による輸出市場の減少と、化石燃料の輸入価格の高騰などにより、貿易赤字が定着するなかで、食料についても自給率の向上を図らなければならないとの政治的な要望が強まっており、米国などとのTPP(環太平洋戦略的経済連携協定)での農作物の関税問題で苦しい交渉が強いられていた。
日本の食糧問題は、世界の平和のなかでの自由貿易に依存する以外に道はない
現在、カロリーベースで39 % 程度とされる日本の食料自給率の値から、食料自給率100% を保証できる日本の人口は、現在(2012年)の人口 1.28億に、食料自給率 39 % を乗じた約5,000 万人と概算される。
一方、10年毎の人口増加比率の年次変化の実績値の延長から推定される2050年の日本の人口は、2010 年に対する人口増加倍率の予測値0.745と2010 年の人口1.28億人から約9,540(= 12,800×0.745)万人と予測される。したがって、この間に国内食料生産量が変わらないとすると、食料自給率は、約 52 %(=1.28×0.39/0.954)にしかならないから、輸入食料にお金を使わなければならない状況は、これからも長く続くと考えるべきであろう。
ところで、日本におけるカロリーベースで39 % の自給率が、世界の先進国のなかでは異常に低い値であることは、表1に示した日本の食料自給率特性値の世界各国の値との比較からも裏付けることができる。
では日本が、食料自給率を上げるには、どうすればよいのか?
先ず考えられるのは、農地面積の拡大である。しかし。森林面積が国土面積の7割近くを占める日本が、その森林からの林業生産物(木材)の7割を輸入に依存している現状で、森林の農地への変換の余地はない。長い歴史のなかで、湿地を干拓したり、山岳地で棚田をつくるなど、農地面積の拡大に苦労してき日本農業の生産力は限界に達している。
次いで考えられるのは、農地での生産性(反収)の増加であるが、効率の良い米作中心の農業が、国民の食嗜好でのコメ離れで、休耕田まで生じている現状で、これも無理な話である。
もう一つ、食嗜好の変換で肉食の制限を進めることも考えられるが、こんなことできるはずがないし、魚類を多食してきた日本では、肉食はそれほど多くはない。
結局は、貿易立国日本のなかで、輸出産業を保護するための自由貿易(グローバル化)を基本としながら、必要最小限の輸入食料を確保するための限定条件付きの貿易協定を食料輸出国と結ぶ以外に食料安全保障を確保する道がないと考える。なお、この食料輸出国との間の2国間の限定条件付きの貿易協定は、国民に十分説明して、その必要性を納得して貰えるものでなければならない。さらには、日本は、世界の自由貿易を根底から覆す国際的な軍事紛争に捲き込まれることが絶対に許されないことも厳しく認識すべきである。
幸い、日本には、第2次大戦の苦い経験から、多数の国民の合意でつくられた、世界に誇る憲法9条の不戦の誓いがある。この憲法9条 の理想を世界に訴え、世界平和を守ることこそが、日本の食料問題を解決する基本でなければならない。
食料の安全保障の基本は、持続的な日本農業の創生でなければならない
かつて、西欧列強は、化石燃料エネルギー資源を使った産業革命で得た軍事力を使って新大陸を含む植民地を増やし、経済成長を遂げてきた。しかし、上記したように、さらなる成長を図ろうとしても、そのエネルギー資源の化石燃料が枯渇に近づいているいま、もはや、それができない。それだけでなく、第2次大戦の苦い経験から、世界の大国が領土を奪い合うような大規模な国際間の軍事紛争を起こすこともないと考えてよいであろう。
もし、それが起こるとすれば、それは、中東の安価な石油資源に関連してであろう。これが、第2次大戦後の国際的な軍事紛争が、主として中東地区で起こっている理由である。さらに、それが、いま、タリバンに始まり、イスラム国に至る国際テロ戦争にまで発展していると見てよい。
しかし、このテロ戦争は、中東の石油の採掘権を支配してきた欧米列強を対象としている。現在、日本もこのテロ戦争の対象になろうとしているのは、米国と軍事同盟を結んで、中東などの軍事紛争の地に自衛隊を派遣しているからである。
いま、日本の安全保障を考えるのであれば、仮想敵国をつくって、軍事力を増強する理由はどこにもない。そのようなお金があるなら、それを、今後、高騰するかも知れない輸入食料代金に充当することを考えるべきである。
この日本の食料問題、すなわち、当面の食料の輸入の問題は、日本の農業政策のあり方と密接に関係する。最近、地域経済の再開発が盛んに言われるなかで、地域産業の中心となる農業の担い手の減少が問題になっていた。
高度成長のなかで、農業の事業採算性が低下した日本の農業は、いわゆる三ちゃん農業と、コメの販売価格を維持するための国の補助金によって何とか命脈を保ってきたと言ってよい。この補助金に対する考え方を、食料の国内生産分で、食料の輸入金額が節減できるとして、この節減分を国が補助金として支給すれば、食料の安全保障のために必要な農業生産量を増やすことができる。
やがてやって来る世界の経済を支えてきたエネルギー資源としての化石燃料の枯渇、すなわち化石燃料価格の高騰は、それを、ほぼ全量輸入に依存してきた日本経済に深刻な影響を与えることは間違いない。その時に備えて、最低限の食料の確保のために必要な農業生産を維持する体制をつくるためにも、上記の世界の食料問題について述べた、持続可能な農業を可能にするコンポストの農地施用を基本とした有機農業方式を、日本は、世界に先がけて創り上げるべきである。
<引用文献>
1.久保田 宏、伊香輪恒男;ルブランの末裔、明日の科学技術と環境のために、東海大学出版会、1978年
2.川島博之;世界の食料生産とバイオマスエネルギー――2050年の展望、東京大学出版会、2008 年
3.久保田 宏、松田 智;幻想のバイオマスエネルギー、科学技術的見地から地球環境保全対策を斬る、日刊工業新聞社、2009年
ABOUT THE AUTHER
久保田 宏;東京工業大学名誉教授、1928 年、北海道生まれ、北海道大学工学部応用化学科卒、東京工業大学資源科学研究所教授、資源循環研究施設長を経て、1988年退職、名誉教授。専門は化学工学、化学環境工学。日本水環境学会会長を経て名誉会員。JICA専門家などとして海外技術協力事業に従事、上海同洒大学、哈爾濱工業大学顧問教授他、日中科学技術交流による中国友誼奨章授与。著書(一般技術書)に、「ルブランの末裔」、「選択のエネルギー」、「幻想のバイオ燃料」、「幻想のバイオマスエネルギー」、「脱化石燃料社会」、「原発に依存しないエネルギー政策を創る」、「林業の創生と震災からの復興」他
平田 賢太郎;日本技術士会 中部本部 副本部長、1949年生まれ、群馬県出身。1973年、東京工業大学大学院理工学研究科化学工学専攻修士課程修了。三菱油化(現在、三菱化学)株式会社入社、化学反応装置・蒸留塔はじめ単位操作の解析、省資源・省エネルギー解析、プロセス災害防止対応に従事し2011年退職。2003年 技術士(化学部門-化学装置及び設備)登録。
4.久保田 宏、平田賢太郎、松田 智;化石燃料の枯渇がもたらす経済成長の終焉――科学技術の視点から、日本経済の生き残りのための正しいエネルギー政策を提言する、私費出版、2016年