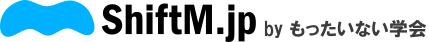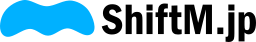Ugo Bardi氏の『嘘の帝国』
本稿はローマ・クラブおよびASPO(association for the study of peak oil)のメンバーで、フィレンツェ大学地球科学学部の物理化学の教授であるウーゴ・バルディ氏のブログCassandras’s Legacy 2016年2月8日付けの記事“The Empire of Lies”を訳したものである。

ダキア(註:現在のルーマニア)の征服においてローマ軍が勝利したことを記念して、トラヤヌスの記念柱は建造された。2世紀のことだ。それは現代人には古風に見える様式ながらも、ローマ人がプロパガンダを知っていて実践していたことを物語っている。当時、まさに私たちの時代と同様に、瀕死の帝国は嘘によって一つに繋ぎ止められていたわけだが、永続することはなかった。
5世紀の初めに、北アフリカはヒッポの司祭アウグスティヌスが『嘘論(”De Mendacio”)』を著した。(訳註:『嘘論』の著述は西暦395年頃とされる。)今それを読むならば、アウグスティヌスが彼の結論においていかに厳格だったか、私たちは驚かされるかもしれない。彼によれば、キリスト教徒はいかなる状況でも何であれ嘘をつくことはできなかった。たとえ命を守るためでも、あるいは誰かの苦しみを和らげるためでさえも、嘘は許されなかったのだ。アウグスティヌス曰く、物質である身体の痛みなど何でもない、重要なことは人間の不滅の魂なのだ、と。後に神学者たちはこのような要求を大幅に和らげた。だが、アウグスティヌスの時代を考慮するならば、アウグスティヌスの厳格な姿勢にも一理あったわけだ。彼が生きた時代とは、西ローマ帝国にとって最後の世紀なのである。
アウグスティヌスの時代までに、ローマ帝国は嘘の帝国になっていたのだ。野蛮人の侵入から人々を守るために、また、社会秩序を維持するために、ローマ帝国はまだ法の支配を支持しているかのような振りをした。だが、すべては帝国の市民にとって悪いジョークになっていた。というのはその頃には帝国は、少数者の特権を温存するために弱者を抑圧することに専従するばかりの巨大軍事機構と言うべきものに成り下がっていたからだ。帝国そのものが嘘になってしまったのだ。道徳的美徳ゆえにローマ人に報いた神の恩寵によって帝国は存在していた。だが、誰ももはやそんなことを信じることができなくなった。社会の根幹が壊れてしまったのだ。昔の人たちが「アウクトーリタス」(訳註:ラテン語の”auctoritas”、「権威」を意味する英語の”authority”の語源)と呼んだものが見当たらなくなって、市民は彼らの国のリーダーや制度を信頼しなくなってしまった。
アウグスティヌスは末期的な事態に応戦しようとしたのだ。彼は、抑圧的な政府の浅はかな権威主義という形ではなく、信頼に足り得る形で、「アウクトーリタス」を再び築き上げようと努めたのだ。そこで彼は、すべてのうちで最高の権威、すなわち神に向かって訴えることになった。彼はまたキリスト教徒が悩める人々を出汁にして手に入れた名声についての論争を吹っかけもした。それだけではない。アウグスティヌスは、彼の書いた文章とりわけ『告白』の中で、自分自身を読者に完全にさらけ出して、細かに思想や罪業を語りかけた。それは、隠れた動機を持たない人間であることを示すことによって、信頼を再構築するための方法でもあった。それゆえ彼は、結論として厳格であらねばならなかった。嘘の帝国に戻してしまうような抜け穴を残すわけにはいかなかったからだ。
アウグスティヌスと他の初期キリスト教の教父たちは、手始めに認識論的な革命に取り組んだ。タルスス(訳註:トルコ南部の都市)のパウロはすでにこの点を理解しており、彼は次のように書き記した。「私たちは、今は、鏡におぼろに映ったものを見ている。だがそのときには、顔と顔とを合わせて見ることになる。」(訳註:新約聖書『コリントの信徒への手紙』13.12)それは真実についての問題だった。真実をどのように見るか?真実をどのように決めるのか?伝統的な考えは、真実は信頼に足る証人によって告げられた。キリスト教徒の認識論はそこから始まり、神のお告げの結果として真実の概念を築いた。キリスト教徒は神を証人(witness)と呼んでいたのだ。これは精神的で哲学的な見方だが、現実的なものであった。今日、私たちはローマ帝国時代末期のキリスト教徒が「リローカリゼーション」に取り組んでいたと言及することもある。彼らはカネがかかる上に防御不可能な古い帝国の構造を放棄して地域の資源と地方自治に基づく社会を再構築しようとしていたと見なせるからだ。そのあとに続く時代、すなわち中世は、衰退の時代と見なされるが、むしろ帝国末期のおかしくなった経済条件に対する必要な適応過程だった。結局のところ、すべの社会が真実を甘受しなければならない。政治的および軍事的構造としての西ローマ帝国はそれができなかった。だが、逃避できなくなるにつれて、帝国は消滅を余儀なくされたのだ。
さて,私たちの時代はどうだろう。奇しくも私たちは私たちの嘘の帝国に到達しているのではないか。現在の状況について、あなたがたがまだ知らない何かを私があなたがたに話す必要があるとは私には思えない。過去数十年の間に、政府によって私たちに投げつけられた嘘の山に完璧に見合うことは、市民がおそろしいくらいに為政者への信頼を失っているということだ。ソビエトが最初の軌道衛星スプートニクを1957年に打ち上げたとき、誰もその真偽を疑うことはなく、西側諸国の反応は自陣営の衛星を打ち上げることだった。だが、今日では多くの人々が、アメリカ合衆国が1960年代に月面に人類を送り込んだことを否定するまでになっている。笑いものにされるかもしれず、陰謀論者のレッテルをはられるかもしれないが、たしかにそういう人々がいるのだ。おそらく、信頼が崩壊した分水嶺は、イラクに隠されていると語られた「大量破壊兵器」の件だった。こういうことは人々にとって初めてのことではなかったが、あれが最後の嘘になるわけでもないだろう。かくもずうずうしくあなたがたに嘘をついた(そしてなおも嘘をつき続けている)制度をどうしてあなたがたはずっと信頼し続けることができようか?
今日、政府からのすべての声明、あるいは関係は薄いものの「公式」とされる出所からの声明は、否認に他ならぬ声明と否認の反対となる声明を引き起こしているように思われる。不幸にも、嘘の反対は必ずしも真実ではなく、それは嘘、嘘の反対、嘘の反対の反対からなる伏魔殿を築いている。ニューヨークの911テロ事件を考えてみよう。この話題にはだんだんと作り上げられていった多くの伝説や神話があり、それらの下に隠されているのだろうが、どこかに真実あるいは真実のようなものがあるにちがいない。だが、ウェブで読む何かを信じることができないとき、真実をどうやって見分ければいいのだろうか? また、ピークオイルのことを考えてみよう。最も単純なレベルの陰謀論的解釈では、ピークオイルは石油資源の減耗を隠す石油企業の嘘に対する反応だと見なされる。だが、ピークオイルを実際には資源が豊富にある事実を隠そうとする石油企業によってつくり出された詐欺だと考える人もいるかもしれない。「無機起源石油」という広く行き渡った伝説では無限に存在するとさえ言われているのだから。だが、他の者にとっては、ピークオイルは石油が豊富にあることを隠すためにつくられた詐欺だという考えこそ石油が欠乏していることを隠すためにつくられたより高次の詐欺であるかもしれない。もっと高次の陰謀論さえ可能なのだ。いわば嘘のフラクタル宇宙であり、そこではあなたがどこにいるのか語るために参照すべき点がないのである。
最終的に、それは認識論の問題となる。ポンティウス・ピーラートゥスの言葉「真理とは何か?」(訳註:新約聖書『ヨハネによる福音書』18.38)に戻ることと同じことなのだ。私たちは私たちの世界で真実を見つけるために、どこを拠り所にしているのだろうか?科学ではどうか?けれども科学は急速に周辺においやられた党派になっており、カタストロフが来るともぐもぐ言っている人々からなる。とても安く供給できるエネルギー、宇宙旅行、空飛ぶ自動車といった約束を果たせなくなるや、誰も科学者を信じなくなるだろう。すると私たちは「民主主義」のような営みから真実を見つけようとして、多数派がどうにかして決める「真実」を信じようとするだろう。だが、肝心の民主主義自体が失われつつあるのだ。また、「認知管理」(昔の言い方では「プロパガンダ」)と呼ぶ概念を発見した後で、市民はどのようにインフォームドチョイス(訳註:情報を得た上での選択)を行うことができるだろうか?
古代のローマ人が辿った軌跡と同じような経路を進んでいるとしても、神の真理の宝庫たるべき法によって考えられた半ば神がかった皇帝がワシントンD.C.に暮らすような状況にはまだ至っていない。そして私たちはまだ古い宗教に取って代わり古い宗教を駆逐する新しい宗教に遭遇していない。目下、公式の嘘に対する反応はたいてい私たちが「陰謀の身構え(conspiratorial attitude)」と呼んでいる形をとる。多分に軽蔑されてしまうけれども、陰謀だとする見方(訳註:原文では” conspirationism ”)は必ずしも間違ってはおらず、陰謀は存在するのであって、ウェブ上に広がる多くの間違った情報は私たちを不利にすることを企んでいる誰かによってつくられるにちがいない。問題は、陰謀だとする見方は認識論の一形式にならないということだ。あなたが読むすべてが大いなる陰謀だと決めてかかるや、あなたは認識論的な箱の中に自分自身を閉じ込めて、鍵を放り出してしまうことになるからだ。そして、ピーラートゥスのように、「真理とは何か?」と尋ねることしかできなくなってしまい、それでいて、決して真理を見つけることはないだろう。
制度への信頼、そして私たちの友である人類への信頼を取り戻してくれる「認識論2.0」について考えることは可能だろうか?おそらくイエスだが、ちょうど今、私たちは鏡におぼろに映ったものを見ている。何かが確実に動いている、外で。だが、それはまだ認識できる形にはなっていない。おそらく、それは新しい考えであり、おそらく古い宗教の再訪、ひょっとすると新しい宗教、はたまた新しい世界の見方なのだろう。新しい真理がどういうかたちになるのかはわからないが、新しい何かは何かの消滅なしでは生まれないということはわかるだろう。そして、すべての誕生は痛みを伴うものの必要なことなのだ。(訳註:「科学者は既成のパラダイムへの信頼を失い、代わりのものを考え始めるけれども、危機に導いた既成のパラダイムを放棄しない、・・・(中略)・・・一つのパラダイムを拒否する決断は、つねに同時に他のものを受け入れる決断である。」(トーマス・クーン/中山茂訳『科学革命の構造』みすず書房、一九七二年、pp87-88))