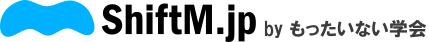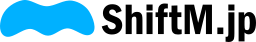COP 21を成功に導くために その1
途上国の経済発展に必要な資金を得るために、温暖化をもたらした先進国の責任が問われている
地球温暖化対策として、先の2013年までの暫定的な各国の温室効果ガス(以下、二酸化炭素に代表されるとして、CO2と略記)の排出削減目標値を決めた京都議定書の協議では、化石燃料の大量消費によるCO2の排出で温暖化を引き起こしたのは先進国であるとして、途上国には、その排出削減義務が免除されていた。
しかし、世界のCO2の効果的な排出削減のためには、途上国の協力も必要だとされ、採用されたのが、CO2排出権取引であった。先進国が開発したCO2排出削減技術を途上国に移転することで、途上国での排出削減量を自国の排出削減量に加算できるとするものであった。しかし、その取引量を左右する単位CO2排出量当たりの取引価格が、この取引を希望する先進国と途上国との間のオークションで決められるとの非科学的な方法が採用されたことで、この制度は、途上国か先進国から経済発展に必要な援助資金を得るために使われたと言ってよい。
この排出権取引制度は、先進国がCO2排出削減量を規定されて、どうしてもそれを守らなければならない条件下でのみ機能する仕組みであった。ところが、京都議定書以降の各国のCO2排出削減量目標値を決めるCOPの協議の場では、経済発展を続けている途上国にも応分のCO2排出削減を実施することが求められるようになるとともに、各国が自主的な削減目標を決めることになり、CO2排出量の超過に罰則規定が無くなったので、先進国にとって、この制度を利用する必然性がなくなった。結果として、途上国にとって、温暖化対策を口実として、先進国から、経済発展に必要なお金を引き出す手段が無くなってしまった。このような状況のなかで、今年の暮れの国連気候変動枠組条約締約国会議(COP 21)の協議の場に出てきたのが「温暖化適応策」である(朝日新聞2015/10/24)。
途上国にとっての温暖化適応策とは、経済発展に必要なお金を先進国から引き出す手段である
いま、このCOP 21 の協議の場で「温暖化適応策」の主体は、最近、その発生頻度と被害規模が大きくなっていると報道されている異常気象への適応策になっているようである。一昨年(2013年)秋から昨年(2014年)にかけて発表されたIPCCの第5次評価報告書では、この異常気象を温暖化によるとしている。このIPCCの発表を根拠に、途上国が、この異常気象による被害を防止ずるための対策費用を今すぐ拠出することを先進国に要求している。すなわち、途上国による自国の経済発展のためのお金を先進国に求める新たな手段として、温暖化適応策が、上記した排出権取引に代わって用いられるようになったと言ってよい。
IPCCは、この温暖化適応策の根拠となっている異常気象が温暖化によるとの主張には、科学的な根拠があるとしている。しかし、異常気象としての例えば台風の規模の増大が温暖化に伴う海水温の上昇によるとして説明できたとしても、IPCCが温暖化の原因としているCO2の排出を削減することで、海水温を下げることができるとの科学的な保証は得られない。いや、世界が協力してCO2の排出削減が実行できるとする保証すら得られていない。であれば、現実的な対応策として、いま起こっている、あるいは、起こるかもしれない異常気象による災害を防ぐためにお金を使う方が、CO2排出削減対策にお金を使うより、費用対効果がより大きいとして、温暖化対策を協議する場に、途上国が持ち出してきたのが温暖化適応策、すなわち異常気象適応策であると言ってよい。先進諸国も、これには異を唱えることができずに、いま、この異常気象適応策が、CO2排出削減を協議するCOP 21 の新たな課題として加わった。
温暖化適応対策に必要なお金はCOP 21 と無関係に拠出されるべきである
それはともかくとして、IPCCが主張するように、異常気象が温暖化のせいだとしても、この異常気象による災害は、温暖化とは無関係な自然災害とともに、先進国と途上国の差別無しに、世界中に大きな経済的な損失をもたらす。ただし、その頻度について考えると、一般に、先進国に比べて、国土面積が広く、また、現代的な防災設備が施されていない途上国のほうが、その頻度が大きいであろう。これが、いま、この防災対策が、途上国で優先的に実施されるべきとしている理由であろう。
さらには、途上国の多くには、このような防災対策を実施する技術やお金が不足している。それが、途上国が、異常気象を温暖化のせいだとして、この温暖化を引き起こした先進国にお金を要求する理由になっている。しかし、上記したように、異常気象が温暖化によるものでないとしたら、この途上国の要請は必ずしも妥当なものでないと考えるが、現実の問題として、経済成長のエネルギー源としての化石燃料を不均衡な形で消費してきた結果として貧富の格差を助長してきた責任が先進国の側にある以上、先進諸国は、可能な限り途上国の要請に応えるべきであろう。
ところで、先進国が、世界の異常気象に対する防災対策にお金を出すとなると、それは自国分とともに二重の経済的な負担を強いられることになる。いま、世界的な経済不況のなかで、先進国が、どこまで、その負担に耐え得るかは別にして、人道上の見地からも可能な限りの努力はすべきであろう。とは言っても、この途上国の要求を、温暖化対策を協議するCOP 21 の場に持ち込むのは、いささか筋が通らない話である。すなわち、あくまでも、いま、世界的に大きな問題になっている貧富の格差の解消の問題として、COP 21 の協議とは区別して、国連の途上国援助(ODA)の枠のなかで、その解決が図られるべきと考える。
その効果が評価できない国内の温暖化適応策には、全面的な見直しが求められる
途上国の要請により、COP 21 で温暖化適応策が取り上げられるようになって、国内でも、温暖化への適応を目的とした「国家適応計画案」が公表され、今後、自治体など各地での適応計画の加速が期待される一方で、対策の効果をどう評価するかなどの課題も残ると報じられた(朝日新聞2015/10/24)。
この新聞報道では、各地の自治体および企業で、すでに始まっている温暖化適応対策例も紹介されているが、問題は、これらの適応策、例えば、「高温に耐える農作物品種の開発」や、「自然災害時の高潮対策」としての堤防の建設計画など、将来、温暖化が起こるとの前提に立っていることである。したがって、この前提がくずれてしまうと、これらの適応対策の開発は無駄になってしまう。
これに対して、いや、温暖化が起こる可能性がある限り、その適応策を用意すべきであるとの考えもあるかもしれない。しかし、何も慌てることはない。温暖化は、そんなに急速に進行することはない。上記した「高温に耐える農作物品種の開発」であっても、南北に縦長の日本列島では、各地の気象条件に適合した農作物の選択に必要な知見は十分蓄積されている。また、「自然災害の高潮対策」についても、すでに、津波対策として、堤防の建設か、住居の高台移転か、避難対策の徹底か、対象地域の立地を考慮した最適な対策を選択するための総合的な研究が、温暖化対策とは無関係に進められている。
では、何故、このような不必要な温暖化適応策の研究が、先走って行われているのかと言うと、それは、国内では地球温暖化対策の名目のもとに、IPCCに所属する研究者の温暖化原因の解明ためのスーパーコンピューターを使ったシミュレーションモデル計算解析の研究をはじめとして、地球温暖化対策関連の事業や研究が、その費用対効果の解析検討が行われないままに、国策として、巨額の税金を使って行われているからである。ここでとりあげた温暖化適応策の研究の費用は、そのほんの僅かに過ぎないであろう。
3.11 の原発事故以降、原発電力代替の電力を生産するための化石燃料の輸入金額の増加に、デフレ対策としての景気の回復と、経済成長を目的として超低金利政策を採ったとったアベノミクスによる円安誘導の結果、貿易収支の赤字とともに、世界一と言われる財政赤字の積み増しに苦しむようになった日本経済にとって、国民に経済的な負担をかけるだけの国策事業や研究は、全面的に見直されるべき時に来ている。その典型例が、京都議定書の時以来、国際的な履行義務があるとして進められてきた地球温暖化対策の国策事業・研究である。本稿(その2)でも述べるように、その対案が明らかにされた以上、いま、国内で進められている地球温暖化対策の国策は、日本経済を破綻の淵に追いやる無駄な事業と断じてよい。