水力発電は日本を救えるか? ダムやさんがつくった「水力発電が日本を救う」?
東京工業大学 名誉教授 久保田 宏
日本技術士会中部本部・副本部長 平田 賢太郎
「水力発電日本を救う」を信じてよい?
朝日新聞 2016/10/30 の書評欄に
竹村公太郎;水力発電が日本を救う、今あるダムで年間2 兆円超の電力を増やせる、
東洋経済新報社、2016 年 (以下。本書と略記)
の書評が載っていた。
この書評の最後に、「化石燃料はいつか枯渇する。原子力は安全性に疑問がつく。であればこその水力発電。読後には(ダムに貯められた雨水は石油に等しい)と言う言葉がハッタリでも誇大妄想でもなく、実現可能な指針と思えてくる」と結んでいる。
しかし、これは、あくまでも文芸評論家としての評者の読後感である。この著書の表題に書かれた「水力発電用ダムで年間2 兆円超の電力を増加させる」ことが、「日本を救える」ことになるかどうかの正しい評価は、文芸評論家ではなく、この国のエネルギー政策についての正しい見識を持った科学技術者によってなされなければならない。
2 兆円超の電力は、現用の国内電力量に対し 1/6強程度?
この著書で、水力発電利用の効用を、2 兆円超の電力を増加させるとして、金額で表しているのは、一般の人に理解しやすいと考えたからではなかろうか?
しかし、科学技術的な効用を訴える著書であれは、水力発電の増加可能量を、通常用いられている kWhの単位を用いて表し、それが、現用の国内の総発電量に対し、どのような位置付けになるのか、すなわち、何%になるのかを、きちんと記述すべきではなかろうか。
いま、対象となっている既設の水力発電設備での電力が、現用の火力発電主体の市販電力を供給できるとしているので、この現状の発電コストを 12円/kWhとすると、2兆円の電力を発電量に換算した値は、
(2×1012円)/ (12円/kWh)= 16.67×1010 kWh
となる。
一方、日本エネルギー経済研究所のデータ(以下、エネ研データ(文献 1 ))から、現在(2014 年度)の 日本の水力発電量の値は8.6859×1010 kWh、国内総発電量は、105.363×1010 kWhで、水力発電量の国内総発電量に対する比率(以下、水力発電量比率とよぶことにする)は8.24 % となる。
また、上記の水力発電の増加量2兆円を、kWhに換算した値は、現在(2014年度)の水力発電量のほぼ1.92(=16.67 / 8.6859 )倍だから、本書で、現用の水力発電ダムで、発電量を増加できるとしている値は、現在の総発電量の 15.8 ( = 8.24×1.92 ) %、= 1/ 6程度にしかならない。「日本を救う」とするのは余りにもオーバーである。
日本の水力発電量比率(水力の総発電量に対する比率)は、世界各国と比べて大きくない
IEA(国際エネルギー機関)の統計データ(エネ研デー(文献1 )に記載)から世界各国の水力発電量のそれぞれの国の水力発電量比率の値を計算して表1 に示した。
この表1に見られるように、国別の水力発電量比率の値では、カナダ、ブラジル、ペルーなど、単位人口当たりの国土面積の広い国で大きな値を示すと見てよい。
これに対して、人口密度の高い日本は、世界各国に較べて、決して、水力発電に恵まれた国とは言えない。
表1 世界各国の水力発電比率(水力発電量のそれぞれの国の総発電量に対する比率)、%、2013年 (IEAデータ(エネ研データ、文献1 に記載)をもとに作成)
| 世界 | OECD 34 | 日本 | アメリカ | カナダ | イギリス | ドイツ | フランス | イタリー | オーストラリア | ニュージーランド | 韓国 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.12 | 13.09 | 7.52 | 6.39 | 60.1 | 1.31 | 3.67 | 12.43 | 18.3 | 7.31 | 53.1 | 1.20 |
| 台湾 | 非OECD | ブラジル | ペルー | 中国 | インドネシア | マレーシア | フィリピン | タイ | ベトナム | インド | ロシア | アフリカ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.18 | 19.0 | 68.6 | 51.6 | 16.67 | 7.82 | 7.68 | 13.3 | 3.46 | 45.0 | 11.9 | 17.1 | 15.8 |
経済成長の停滞で日本の水力発電量比率の年次減少が止まった
現在、電力の生産方式として水力、火力、原子力、さらには再生可能エネルギー(再エネ)としての新エネルギー(新エネ)が用いられているが、そのなかで、水力は、最も古くから用いられてきたコストの安い電力であった。
経済の発展とともに、電力需要の増加分が化石燃料を用いた火力発電に依存するようになる一方で、立地条件に制約のある水力発電量比率は、年次、減少していった。
日本の水力発電量比率の年次変化を図1 示す。
高度経済成長時の、急激な減少の後も、水力発電比率は、減少を継続したが、成長が止まった2005年度頃になって、やっと、8 % 程度で、下げ止まっている。
しかし、経済成長に必要な主なエネルギー源の化石燃料が、やがて、枯渇することを考えると、いずれは、国民の命と暮らしを守るためのエネルギーの全てを、再生可能エネルギー(再エネ)に頼らなければならない時が来る。
この再エネ電力としては、本書に記載された、安価で、今すぐにも導入可能な既存の水力発電設備の運転方法の改善による発電量の増加を図るべきである。しかし、上記したように、この既存の水力発電設備での発電増加量は、現状の国内総発電量に較べて余り大きくないから、本書の表題にあるように、「日本を救う」とは言えない。

図1 日本の水力発電量比率(総発電量に対する水力発電量の比率、%)の年次変化
(エネ研データ(文献1 )をもとに作成)
また、いま、化石燃料の代替として、その利用・普及が期待されている水力発電以外の再エネ(新エネ)電力は、現状では、化石燃料による火力発電よりも安価な電力として、今すぐには導入できない。
したがって、現状のエネルギー源の主体になっている化石燃料のほぼ全量を輸入に依存している日本で、化石燃料の枯渇に備えるためには、先ず、可能な限りの電力消費の節減(節電)に努めなければならない。
その上で、化石燃料火力発電のコストより安くなった新エネ電力の種類を選んで、順次、利用・普及を拡大して行き、最終的に、発電量の全量を在来の水力発電も含んだ再エネ電力のみを利用する社会に移行すればよい。
多目的ダム方式水力発電設備の年間平均設備稼働率は年次低下していた
発電設備の発電能力(発電設備容量で表される)は kWの値で、また、発電電力量(発電量)は kwhの値で与えられ、両者の関係は次式で与えられる。
(年間発電量、kWh )
=(発電設備容量、kW)×(発電設備の年間平均設備稼働率)×(8,760 h/年) ( 1 )
エネ研データ(文献 1 )から、電気事業用と自家用を合わせた国内の水力発電(合計)について、発電設備能力と発電電力量の年次変化を図2に示した。
この図2 に見られるように、国内水力発電(合計)の発電設備容量の値は、年次、ほぼ、直線的に増加しているのに発電量は変動はあるものの、1990年度以降、ほとんど変わっていない。

図2 国内水力発電(合計)の発電設備能力(発電設備容量 kW)と発電電力量(kWh)の年次変化 ( エネ研データ(文献 1 )をもとに作成)
この図2 のデータから ( 1 ) 式を用いて、国内水力発電(合計)の年間平均設備稼働率の値を求めて、その年次変化を図3に示した。

図3 国内水力発電(合計)の年間平均設備稼働率の年次変化、
(エネ研データ(文献1 )をもとに作成)
この図 3に見られるように、国内水力発電(合計)の年間平均設備稼働率の値は、年次大幅に減少しており、2014年度には20 % にまで落ち込んでいる。
これが、図2 に示すように、水力発電の設備能力が年次増加しているのに、発電量が伸びない理由になっている。
現状の日本の水力発電方式は、いわゆる貯水式(ダム方式)が用いられているが、このダム方式の水力発電設備の年間平均設備稼働率の値が年次低下する主な理由としては、発電用に用いられているダムの多くが、いわゆる多目的ダムとして建設されているからであろう。
すなわち、この多目的ダムの貯留水は、発電用以外の飲料用、農業用、工業用など、多様な目的に用いられており、これらの発電用以外の用途に用いられる水量が、経済の発展につれて、年次増加するために、水力発電用に用いられる水量が年次減少していると考えられる。
であれば、この年間平均設備稼働率の値は、地域によっても変化してもよいと考えられるので、今年(2016年)の電力制度改正以前の旧電力会社別の水力発電の年間平均設備稼働率の値(2014年度)を計算して表2に示した。
この表2 に見られるように、予想,した通り、大都市圏を含まない地域(旧電力管内)の北海道、東北、北陸の各電力管内で、自家発電を含む国内合計の水力発電での20 % よりやや高い設備稼働率の値を示している。
表 2 地域別(旧電力会社別)の年間設備稼働率の値、%、2014 年度
(エネ研データ(文献1 )をもとに計算して作成)
| 地域(電力会社) | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 国内計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年間平均設備稼働% | 26.9 | 38.5 | 13.2 | 18.7 | 37.7 | 19.2 | 13.4 | 6.99 | 13.1 | 20.0 |
多目的ダムの発電可能量は、現状の2 ~3倍にできる?
図3に示すように、水力発電(合計)の年間平均の発電設備稼働率の値が、現在、20 % 程度もの低い値をとる理由として、もう一つ考えられるのが、台風が年に何度もやって来る日本列島で、この多目的ダムの大きな役割になっている治水対策である。
この著書でも、ダムの貯水量は、満水時の半分程度で、これが、発電設備稼働率を低下させる主な原因になっていると記している。
これは、多目的ダム方式の水力発電の発電設備容量の値が、実際の発電可能量とは無関係に、ダムの満水時の水量を基準にして決められているからであろう。
もともと、日本の河川水は、稲作の灌漑用として、農業に水利権があった。この農業用の水利権を残したまま、発電用の河川水の有効利用を目的とした大規模なダムが建設されるようになった。これが、第2次大戦後、大量につくられるようになった多目的ダムで、その重要な目的に治水対策があった。
昭和30年代に決められたこの多目的ダムについての法律では、治水の目的が重要視され、何時襲ってくるか判らない台風に備えて、ダムの貯水量が規制されるようになった(この著書から)。結果として、発電に使われる水量が大幅に削減され、満水時を基準とした発電設備容量の値に対する年間発電量の値、すなわち、上記 ( 1 ) 式で計算される水力発電の年間平均設備稼働率の値が大幅に低下することになった。
なお、この治水対策に影響される水力発電の年間平均設備稼働率の値は、ダムの立地によっても左右されることが考えられる。したがって、エネ研データ(文献1 )から計算して作成した図4に示すように、ダム用の河川が企業用に独占使用されている自家発電(水力)設備では、この年間平均稼働率の値が、商業用の電力生産を主体とする水力発電(合計)の値に較べて、高い値を示す。ただし、自家発電(水力)の値は、2005年ごろから、水力発電(合計)の20%近い値に急増しているが、それまでは、8 % 程度以下であった。

図4 自家発電(水力)の年間平均設備稼働率、水力発電(合計)との比較
(エネ研データ(文献1 )をもとに作成)
しかし、このダムの治水対策に関する法律が制定された時から60年以上も経った現在、気象観測技術は格段に進歩している。現在は、台風の規模や進路などがかなり正確に予測できるようになった。
したがって、この予測に従って、洪水対策としての貯水量の調整を科学的に行って、発電用に利用できる水量を増加させることができれば、現有のダムで、発電量を大幅に増加させることができる。
これが、この著書で、現状の水力発電設備を使って、発電量を現状の2 ~3 倍も増やせると主張する理由である。
水力発電で日本を救うことは難しいが、その最大限有効利用を図るべきである
水力発電にはダム方式の他に、貯水用のダムを建設しない流水方式の中小水力とよばれている発電方式がある。
この中小水力の導入可能発電設備容量は、環境省の再生可能エネルギー導入ポテンシャル調査報告書で14.44×106 kWとあり、年間平均設備稼働率を65 % とすると、年間発電可能量は 8.2×1010 kWhとなり(文献 3 参照)、現在(2014年度)の水力発電量にほぼ近い値になる。
したがって、ダム式の発電量を、この著書にあるように、現在の発電量の2倍に増加させることができたとして、これにこの流水方式の中小水力を合わせた将来の水力発電量の可能発電量の予測値は、
( 8.7×1010 kWh )×2 + 8.2×1010 kWh.= 25.6×1010 kWh
となる。
しかし、この値でも、現在(2014年度)の国内総発電量 105×1010 kWhの1/4 程度に止まるから、この著書の書評のタイトルにあるように、「実は資源大国、有効に使おう」の前半部の「資源大国」には、ほど遠い値である。
もちろん、後半部の「有効に使おう」は、まさに、その通りで、確かに、量は少ないが、他の再エネ電力に較べて、比較的安価な電力を供給できることから、この水力発電は、可能な限り有効に使う努力が必要である。
問題は、この「日本を救う」とまでは言うことのできない水力発電を、「ハッタリでも誇大妄想でもなく、実現可能な指針と思えてくる」とするこの新聞の書評のあり方である。
本書のような国のエネルギー政策の問題に関する科学技術書の評価は、その影響力の大きさから、豊かな知識と判断力をもった科学技術者に委ねるべきであることを、この新聞社の書評欄の担当者にお願いしたい。
<引用文献>
1.日本エネルギー経済研究所 計量分析ユニット 編;EDMCエネルギー・経済統計要覧2016, 省エネルギーセンター、2016年
2.久保田 宏、平田賢太郎、松田 智;化石燃料の枯渇がもたらす経済成長の終焉――科学技術の視点から、日本経済の生き残りのための正しいエネルギー政策を提言する、私費出版、2016年
3.久保田 宏;科学技術の視点から原発に依存しないエネルギー政策を創る、日刊工業新聞社、2012年
ABOUT THE AUTHER
久保田 宏;東京工業大学名誉教授、1928 年、北海道生まれ、北海道大学工学部応用化学科卒、東京工業大学資源科学研究所教授、資源循環研究施設長を経て、1988年退職、名誉教授。専門は化学工学、化学環境工学。日本水環境学会会長を経て名誉会員。JICA専門家などとして海外技術協力事業に従事、上海同洒大学、哈爾濱工業大学顧問教授他、日中科学技術交流による中国友誼奨章授与。著書(一般技術書)に、「ルブランの末裔」、「選択のエネルギー」、「幻想のバイオ燃料」、「幻想のバイオマスエネルギー」、「脱化石燃料社会」、「原発に依存しないエネルギー政策を創る」、「林業の創生と震災からの復興」他
平田 賢太郎;日本技術士会 中部本部 副本部長、1949年生まれ、群馬県出身。1973年、東京工業大学大学院理工学研究科化学工学専攻修士課程修了。三菱油化(現在、三菱化学)株式会社入社、化学反応装置・蒸留塔はじめ単位操作の解析、省資源・省エネルギー解析、プロセス災害防止対応に従事し2011年退職。2003年 技術士(化学部門-化学装置及び設備)登録。
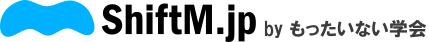




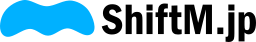
考え方に大賛成です。
事業継続計画 BCP(Business Continuity Planning) につながります。小規模発電(再生可能エネルギー)はITを活用してもっと結合、発展できます。
ダムがもつ水の位置エネルギーをもっと見直したいです。ダムの湛水率はもっと上げられます。リチウムイオン電池の最大充電率がBMSの進化で上がったようにダムの湛水もリスクを考慮して上げられると思います。