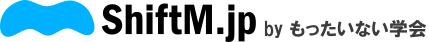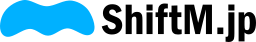日本近海のメタンハイドレートは資源でない
日本近海のメタンハイドレートは資源でない
——フェーズ1報告を読んで
田村八洲夫
フェーズ1までの経緯
メタンハイドレート層の存否は石油調査で良く使われる「地震探査記録」から推定される。世界的には1970年代後半から、日本近海で1980年代初頭から注目され、科学的な調査研究が進められてきた。そして2000年に、日本近海には、その推定されるメタンハイドレート層の広がりが、大・小・豆粒の大きさ100か所以上に分かれ、合わせて約44,000km2に及び、その中に7兆m3のメタンガスが存在し、日本の消費量の100年分の天然ガスに相当すると広報された。これによって、メタンハイドレートは有望な国産資源であり、日本は資源大国になれるのではないか、というユメが語られた。
そして経済産業省の主導の下で、「メタンハイドレート資源開発研究コンソーシアム」が(独)石油天然ガス・金属鉱物資源機構(JOGMEC)、(独)産業技術総合研究所(AIST)、(財)エンジニアリング振興協会(ENAA)を中心に、2001年から18年間(予定)にわたる大型の開発研究プロジェクトとして取り組まれた。三組織から委託又は外注された約30の企業・大学・研究機関、約300人の研究者が、高いセキュリティの下で参画しているようで、ムラが形成されているようである。毎年100億円水準の研究費が投入されているといわれている。2011年に、メタンハイドレート資源開発研究フェーズ1(主に基礎的研究、資源量評価)の報告(以下、『フェーズ1報告』と略称)がなされた。
フェーズ1のミッションは資源としての評価
資源とは、石油にしろ、ガスにしろ、ウランにしろ、「濃縮され、大量にあり、経済的な位置にあるもので、中でも濃縮が根本(石井吉徳)」である。海水中の金、ウランのように拡散して存在しているものは、総量が多くても資源ではない。
国民から見て、フェーズ1の第一義的なミッションは、メタンハイドレートが資源にかなうものかどうか、その質を評価することであると思う。よって資源の定義を基に、メタンハイドレート資源開発研究フェーズ1の概略評価を試みる。なぜ概略評価かというと、詳細なデータが国民の前に開示されていないからである。
フェーズ1報告によると、日本近海の推定メタンハイドレート層分布の2009年版が作成されている。この間に佐渡沖南西域で詳細地震探査、東部南海トラフ海域沖で詳細地震探査と32坑井のボーリング調査が実施され、既存データの全体見直しがなされたと思われる。この改訂版によると、推定メタンハイドレート層分布のエリアは、122,000km2(2000年版の2.77倍)に広がっているが、さらにメタンハイドレート推定の確からしさを4つのランクで区分している。東部南海トラフ海域はトップのランク1で、メタンハイドレート凝集帯の存在が確認されたとするエリアである。メタンハイドレートの新たな推定存在量が明示されていないが、増えたエリアの多くが、より不確かなランク3、ランク4のためであろう。
タンハイドレート層の濃縮の程度を評価
ここで、メタンハイドレート層の濃縮の程度を評価する。
東部南海トラフ海域エリア約5,000km2で16ヶ所の凝集帯が発見された。その原始資源量は5,739億m3、凝集帯を除く部分での存在量5,676億m3、合計1.1兆m3と評価された。さらに16ヶ所の凝集帯の中で試掘対象の優れたものが選ばれた。そのひとつがα―1凝集帯で、生産シミュレーションによる回収率が32%であり、通常の天然ガス生産回収率が約70%と比べて非常に低い。16凝集帯の一つ当たりの原始資源量は平均360億m3である。そのメタンガス回収量(可採埋蔵量)は115億m3で、日本の最近の天然ガス消費量815m3/年として、52日分の生産量である。5000km2のエリアに大小分散している16凝集帯を合わせても、推定可採埋蔵量は1840億m3、日本の消費量の2年分余りに過ぎない。 なお、凝集帯とみなせない賦存層の推定存在量5,676億m3は、開発困難として排除する。
元へ戻って、日本近海の推定存在量7兆m3に機械的に前述の回収率32%かけるとメタンガス2.24兆m3で、32年分の消費量に過ぎない。これが122,000km2のエリアに100個以上に分散している。一例として、ロシアのオレンブルグガス田は、同程度の可採埋蔵量を有した100km×25kmドーム構造で、産ガス面積は1320km2に濃縮している。日本近海のメタンハイドレートガスが、その100倍近い面積に拡散してエントロピーの高い状態で存在している。それを濃集するには拡散の度合いに対して、幾何級数的なエネルギーが必要であろう。これは誰も日t礼できないエントロピーの法則である。到底、国内消費量の100年分は生産できるとは誰も言えないはず。
濃縮の程度から見た場合、資源と評価しうるのは、フェーズ1報告を通覧して東部南海トラフ海域の限られるとみるべきである。日本の消費量の2年分余りのメタンガス量である。
メタンハイドレート生産能力の限界
次に、メタンハイドレートガスの生産能力について、フェーズ1報告を基に検討する。α―1凝集帯での生産シミュレーションによると、1坑井当たりの平均ガス生産レートは約2000万m3/年であり、通常のガス田の生産能力より一桁小さい。その理由は、ガス自噴しないため。よって化学的に分解させる。しかしメタンハイドレート分解が吸熱反応であるために低圧化だけでは生産障害に至るので、加温しながら低圧分解させるという複雑な操作になる。また地層内流動できないため、約500m間隔で、多数の生産坑井が必要となる。凝集帯1つ当たりの平均的なメタンガス回収可能量は、前述の115億m3として、15年で回収だと39本の生産井が必要となる。16か所の凝集帯に対して総計624本の勘定となる。こう考えると、通常の天然ガス開発と比べて、開発生産システムの建設と運転に多量の良質エネルギー、資材、コストがかかることは容易に想像される。しかしこのあたりの試算、とりわけ投入エネルギーの質と量、システムのエネルギー収支比(EPR)がなされていない。
メタンハイドレート開発には、周知のように海底環境に対するリスクがある。メタンハイドレート層が未固結の柔らかい堆積層であるため、掘削、生産によって、思わぬ地層圧変動、地層変形、流動などが起こり、海洋底地形、深海底生態、メタンガス漏えい、海洋汚染が挙げられる。いったん起こると、甚大な損害、被害が、広域的に起こりうる。
フェーズ1報告を見て、海外の政府系機関との国際協力がなされている。しかし、世界の石油会社、例えば、エクソンモービル、BP、シェルなどからのビジネスアプローチがあるのか、旨み味あれば、必ず動く彼らの食指はどうなのかどうかわからない。
石油減耗の時代にキッズを偽らないようにしよう
フェーズ1を終えて、日本近海のメタンハイドレートの分布がそれほど濃縮されたものでなく限られていること、最有望な東部南海トラフ海域でも、日本の天然ガス消費量の2年半程度の回収量予測であるがわかる。これらを、「これからの技術開発で何とかなる」と気負っても限界があることを認識しよう。日本のキッドは、「メタンハイドレートで日本は資源大国になる。100年分ある」と叩き込まれ、ユメでなく事実のように思い込んできている。10年前ならユメとして語ってよかったと思うが、今の時点でやめよう。キッドを裏切る恐れになるような語りはやめよう。
良質の石油が減耗する時代が間もなくくる。メタンハイドレート生産のEPRは低く、場合によれば1以下になるかもしれない。石油減耗期に、そのようなエネルギー開発に、貴重な良質な石油を多量に使うことを社会が認めるとは思えない。