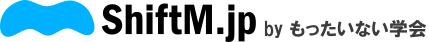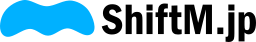エネファームは、家庭の「オール電化」を訴えていた電力会社に対抗する都 市ガス供給会社の企業戦略であった
科学技術の視点から、どう考えてもおかしい「水素社会」 :その4
燃料電池車(FCV)とともに「水素社会」のフロントランナーとして、その利用の普及・ 拡大が期待されているのがエネファーム(燃料電池による家庭用電力の供給設備)である。 しかし、「水素元年」のシンボルとされた FCV が庶民の自家用車として用いられることが あり得ないことを、先の本稿(その2)で明らかにした。では、エネファームは、「水素社 会」の基幹技術となり得るのであろうか?
エコキュートからエネファームへ、家庭用給湯器を巡る仁義なき戦い
3.11 の原発事故が起こる以前には、よく、東京電力の代理店と称するところから家庭用 の給湯器としてのエコキュートの売り込みの電話がかかってきた。エコキュートでは、ヒ ートポンプの原理を使って、電力をエネルギー源として動力を熱に変換している。この電 力が夜間の安価な原発の余剰電力(9 円/kWh 台)で賄われることで、消費者にとって安価 な家庭の給湯用温水を供給できるとして、対抗する都市ガスや LPG をエネルギー源とする ガス給湯器の市場を奪う形で、急速に売り上げを伸ばしていた。これに危機感を持ったガ ス会社や石油会社が、共同で開発し、共通の商品名で売り出したのがエネファームである。
エコキュートが家庭用エネルギー供給でのオール電化の企業戦略の一つとして、その開発が進められたのに対抗して、ガス会社が開発したエネファームは、各家庭に設置した設 備内で、都市ガス(あるいは LPG)を原料として水素をつくり、この水素をエネルギー源 とした燃料電池で電力を生産することで、家庭用電力供給の仕事を電力会社から奪いとる 仕組みになっている。同時に、給湯用の温水の製造には、都市ガスから水素を製造する際 の発熱反応の廃熱が利用されている。すなわち、エネファームは、オール電化を謳い文句 にした電力会社による家庭用のエネルギー供給事業に対抗して、都市ガス供給業者等が、 家庭用のエネルギー供給事業を独占する目的で開発されたと言ってもよい。
たまたま、このエネファームの売り出しの開始時期が、3.11 の原発事故と重なり、原発 電力を使うことで拡販を自重せざるを得なくなったエコキュートに代わって、現状で、エ ネファームが、確実に、市場を伸ばしているようである。
エネファームの利用による家庭用エネルギー消費の節減効果は大きくない
家庭用のエネファームの使用が、一般に広く普及するためには、その使用で、消費者に とっての経済的なメリットがもたらされなければならない。私が、東京ガスのエネファー ムの宣伝用のパンフと営業担当の技術者から聞き取ったデータから、都市ガスをエネルギー源としたエネファームの使用での都市ガスの消費量は 0.2057 Nm3/kWh と計算される。 したがって、都市ガスの消費量の増加を促すための割引料金 117 円/Nm3 の適用でも、発電 コストは、24 ( =0,2057×117 ) 円/kWh と計算され、市販の家庭用電力料金と変わらないから、このエネファーム利用での電力生産では、消費者の経済的なメリットは得られない。
すなわち、エネファームの使用での消費者の利益は、都市ガスを用いた燃料電池原料水素 ガスをつくる際の廃熱の利用による給湯用の都市ガス使用料金の節減効果にあるとしてよ い。しかし、この家庭の給湯用のエネルギーを、燃料電池用の水素製造の際の廃熱で賄う 際には、この発熱量と、家庭での給湯の需要熱量とのバランスが問題になる。一般的には、 廃熱量が、通常の給湯の需要熱量を大きく上回るので、廃熱温水を、給湯用とともに床暖 房用にも利用することが、エネファームの標準的な使用条件になっている。
いま、この廃熱の 100 % 利用を仮定した場合の標準家庭の一世帯当たりの都市ガス使 用での節減金額を計算してみる。エネファームパンフから、単位発電量あたりの都市ガス 節減量は 0.1041 Nm3/kWh とあり、都市ガスの通常の市販料金 150 円/Nm3 から、都市ガ スの節減金額は、15.62(=0.1041×150 )円/kWh となる。エネルギー経済研究所のデー タ(文献 3 -1)で、2010 年度の家庭部門の平均電力消費量は 475 kWh/月とあるので、エ ネファームの使用による家庭用のエネルギー消費の節減金額は、次のように計算される。
(15.62 円/kWh)×(475 kWh/月)= 7,420 円/月= 8.9 万円/年
市販設備価格 180 万円から国の補助金 30 万円を差し引いた消費者の支出金額 150(= 180 – 30)万円を償却するには、16.8 ( = 150 / 8.9 )年が必要となり、エネファームの使 用期間(燃料電池の寿命)とされる 10 年間を大幅に上回ってしまう。
ただし、この償却年数の値は、政府が、このエネファームの利用・普及を拡大するため の設備購入の際の補助金、一基あたり 30 万円を支給している条件下での値である。実は、 この補助金の支給額には科学的な根拠がない。「補遺 3-1」に記したように、私どもが提案 している省エネ製品としてエネファームの適正補助金額を 15.8 万円(計算方法は、文献 3-2. 参照)とした場合には、償却年数 18.4(=(180- 15.89) /8.9 )年と、さらに大きくな る。
消費者にとっての設備償却年数を設備の使用年数 10 年以内に納めるためには、設備価格 を現状の半分近い 100 万円以下に低減させることが必要になる。結局、当面は、将来的な 家庭用電力料金の値上がりをあてにし、消費者のボランテイアに依存して、その販売促進が 行われることになる。
また、以上の試算では、電力生産での廃熱が 100 % 利用できた場合を想定しているが、 実際のエネファームの使用では、給湯用の廃熱量が、その需要量とはバランスしないから、 廃熱の利用比率は、大幅に低下する。この設備償却年数は、上記したように、廃熱の利用 比率にほぼ反比例するから、例えば、廃熱の利用率が 50 % に止まれば、償却年数が 2 倍 になってしまう。
さらに、より大きく問題になるのは、このエネファームの利用は、燃料電池原料の水素が、天然ガスから製造される現状でなり立っていることに注意する必要がある。すなわち、 天然ガスが枯渇し、燃料電池用の水素の製造を再生可能エネルギー電力(再エネ電力)に 依存しなければならないとしたら、水素製造の際の廃熱が利用できなくなるから、家庭で の給湯用のエネルギー利用による利益が失われてしまう。
エネファームは、本来、「水素社会」とは無関係な存在である 。
「その 1 」で述べたように、いま、エネファームは、FCV とともに水素社会のフ ロントランナーのように言われている。しかし、それは、エネルギー供給システムとして のエネファームの中心に燃料電池があり、そのエネルギー源が水素だからという理由だけ で、メデイアが勝手に言っていることである。現状では、この水素は、天然ガスや石油(LPG) からつくられる水素であるが、この水素原料の化石燃料が利用できなくなったときには、 家庭用のエネルギー供給システムとしてのエネファームは、その存在意義を失ってしまう。 すなわち、電力は、直接、再エネ電力か、あるいは、原発電力で賄われればよいし、給湯 用のエネルギーも、太陽熱が大幅に利用されるべきで、水素の出番はなくなる。
改めて、MIRAI の立派なカタログ(表紙込みで 56 ページ)を見直してみると、その表 紙の裏に、六角形(ベンゼン核?)のなかの H2 がビルの合間の空に浮いているのを指さす 少女の絵とともに、「おはよう、未来」の表題で、・・・水素の本格的なエネルギー利用が 世界に先駆けて始まります・・とあり、至る所に、ふんだんに、水素の文字が躍っている。 これに対して、東京ガスのエネファームの 8 ページのパンフには、どこを探しても水素の 文字は見当たらない。もともと、エネファームは、そのメーカにとっては、水素社会とは 無関係な存在だったのである。
「補遺 3-1 」省エネ・創エネ製品の普及促進のための補助金の適正支給金額を決める方法
いま、省エネ製品(省エネ家電製品など)や再エネ電力の生産のための創エネ設備(太陽光や 風力発電設備など)の利用・普及を促進するためとして、消費者に、これらの購入の際の補助金 を支給する制度が広く用いられている。すなわち、単に、これらの製品の販売を促進するためと して、国民のお金(税金)が、例えば、上記(本稿(その2)で述べたように、FCV では 700 万円の販売価格に対し 200 万円(販売価格の 28.6 ( = 200/700 ) %)が、EV に対しては 280 万 円に対し 53 万円(18.9 ( = 53 / 280 ) % )が、支出されている、しかし、これらの補助金支給 額の決定には、何の科学的根拠も示されていない。
これに対して、私は、これらの省エネ製品・創エネ設備の使用による国民にとっての経済的な 利益は、エネルギーの主体を輸入化石燃料に依存する日本の現状では、これらの省エネ、創エネ による輸入化石燃料の節減金額として評価できるから、補助金の支給額は、次のよう決められる べきであると提案している。
(省エネ・創エネ製品の購入に対する適正補助金額) =(省エネ・創エネ製品の使用による化石燃料の輸入金額の節減額) -(省エネ・創エネ製品の製造・使用に要するエネルギー消費を稼ぎ出すために必要な国 民の支出金額)
この(適正な補助金額)の決め方を用いることによって、はじめて、化石燃料の輸入金額によ る貿易赤字に苦しむ日本経済にとって、国民の経済的な負担を強いることのない省エネ、創エネ の推進のための合理的な補助金額を決めることができる。具体的な計算の方法については、文献 3-2 を参照されたい。
引用文献;
3-1.日本エネルギー経済建久所計量分析ユニット 編;エネルギー・経済統計要覧、2014, 省エネセンター、2014 年
3-2.久保田 宏;脱化石燃料社会、「低炭素社会へ」からの変換が日本を救い、地球を救う、化学工 業日報社、2011 年