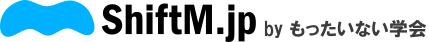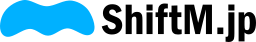温故知新 ~ローカライゼーション考~
経済が行き詰まると田舎ブームが沸き起こる。
「リ・ローカライゼーション」という耳慣れない言葉が囁かれているが、戦前の日本でも「土に還れ」との哲学が説かれ、農業を基盤としたローカル・コミュニティの再生を目指す動きがあった。坂口安吾は「戦争中は農村文化へかえれ、農村の魂へかえれ、ということが絶叫しつづけられていた」(『続・堕落論』)と記していたが、私としては、五・一五事件に関与した農村活動家・橘孝三郎の軌跡を想起せずにはいられない。
「人間は歴史から学ばない、ということを私たちは歴史から学ぶ」とはヘーゲルの警句だが、「リ・ローカライゼーション」とやらの行く末に同じ轍を踏まないためには、歴史を学んでおくのも悪くはないだろう。
それは戦前の話。明治維新以来の文明開化の流れは、いよいよ第一次世界大戦の終結によって頓挫した。当時の覇権国家大英帝国中心の世界秩序が崩壊して、世界経済は大きな混乱期に突入、日本は出口の見えない深刻な不況に陥ったのだ。明治維新以来の自由競争社会の中で貧富格差が拡大し、文明開化から取り残された貧しい層が形成されていたが、以前にも増して格差拡大、不満と失望が国民各層に広まっていった。追い討ちをかけるように、関東大震災(一九二三年)が発生し、鬱積した矛盾は金融恐慌(一九二七年)となって一挙に吹き出した。さらに、世界恐慌(一九二九年)の荒波に襲われ、失業者数は激増、凶作飢饉によって欠食児童や娘の身売りが続出、農村も都市も病態化、日本は一九三〇年代に未曾有の激動期を向かえることになった。浜口首相狙撃事件、満州事変、血盟団事件、五・一五事件・・・と不穏な事件が続いた。
とりわけ一九三二年に起った五・一五事件は、日本が軍国主義へと流れる歴史の転機を与えた事件と評されている。海軍の青年将校や農民有志らが、要人の暗殺、銀行や変電所の破壊を図って決起した事件だ。変電所を破壊して帝都を停電にする計画は果たされなかったが、犬養毅総理大臣が凶弾に倒れた。この事件によって、戦前の政党政治は機能しなくなった。
当時の人々は、卑劣なテロに反感をもちつつも、メディアが事件の犯行動機を人々に伝えるに連れて、次第に五・一五事件の決行者に共鳴していったそうだ。生活苦こそが犯行動機であり、一〇〇万通に及ぶ減刑嘆願書が集まり、新聞・雑誌には被告を讃える記事さえ掲載されるような事態へと展開していったらしい。五・一五事件は政党政治が作り出した社会悪に対する「義憤」から生まれた事件として同情的な論調が醸されていったのだ。不幸にも、そのような論調こそが、政党よりもクリーンなイメージを保持していた右翼と軍部の影響力を強めて、凄惨なクーデター二・二六事件を誘い、恐怖支配によって日本は戦争の泥沼へと突き進んでいったわけだ。
五・一五事件が日本の歴史の転機を与えたとされるわけだが、五・一五事件に関与した農村活動家・橘孝三郎の思想と評伝は、これからの時代を展望する上で教訓を与えるように思われる。というのは、橘は、農業を基盤としたローカル・コミュニティの再生を試みて挫折した挙句、急進的な社会改革を期して五・一五事件に関与したからだ。そして、橘が獄中で残した言葉は、現代社会が直視すべき課題とも言えるからだ。
橘孝三郎は旧制第一高等学校時代、人生に煩悶、人間らしい正直な暮らしを求めて一九一六年、二二歳で郷里の茨城県で農業を始めた。不運にもその二年後、第一次世界大戦が終結し、橘は一九二〇年代のデフレ不況の只中を過ごすことを余儀なくされた。追い打ちをかけるように、関東大震災と世界恐慌が襲う。国民生活の疲弊は深刻化していたが、農産物価格の大幅な下落は農民の生活を直撃した。
そして橘は、「日本の百姓の立場から、日本国民社会の「予後最も危うき」病態状態の病根のある処をたしかめずにおられなくなって」、彼の農本主義思想の集大成とも言える著書『農村学』を著し、また、模範的農家の育成を目的とした私塾「愛郷会」を創立した。
橘は、一九二〇年代の資本主義諸国の行き詰まりと退廃した社会の病根を「資本主義の破農性」にあると指摘し、資本主義の営利精神に打ち克つ農民の勤労と協力団結にもとづく理想社会の建設を夢見るに至った。まさに農業を基盤とするローカル・コミュニティの再生を目指したわけだ。
橘は、「産業及び其他の資本主義経済組織が都市を基礎とし中心として行われ」、「農村自らはその犠牲たらざるべからざるところ終に死に迄搾取されるため以外の何物を表していない」と言って、明治維新以来の金力支配・都市中心主義的な社会のあり方に悲憤慷慨、農村が荒廃して都市が繁栄する道理はないとして、「過去において都会生活に破れた者共をあたかも放蕩息子を迎えるように喜び迎えた農村ももう瀕死なのだ。最初に救われなくてはならないのは放蕩息子ではない。蓋し好況に次ぐに好況をもってした過去は農村を救うべきための何物でもあり得なかったのである。救うどころか表面の好況はその度を倍加した勢いにおいて魔手を見えざるに広げていった資本主義破壊性の発達への好機会に過ぎなかった」、「我々は今や勤労生活を捨てて強力団結を解消し、土を滅ぼして自滅せんとしている。しからばなすべきこともまた自ら明らかではないか。我々は今や正に土に還らなければならない」、「土に還れ、土に還れ。土に還ってそこから歩行の新なるものを起こせ。それのみが自己と他と一切を開放すべく我等に示されたる唯一の途である。それのみが都市農村と全国民社会を救うべき大道である」と説いた。
だが、農民の自助努力だけでは生活がまるで改善しないという現実に橘は悩んでいた。「都市農村と全国民社会を救うべき大道」と大見得を切ったものの、まるで報われない現実に懊悩するしかなかったのだ。そんなときに、軍部の「革新派」との邂逅があり、橘は農村救済のための急進的社会改革を求めて右翼陣営に身を投じたのだ。橘は五・一五事件に参画、満州に渡り、潜伏先で「国民共同体王道国家農本建設論」と題する論文を書き上げて、七月二四日にハルビン憲兵隊に自首をした。
小菅刑務所に入獄後、橘孝三郎はローマ史と金融論を中心とした読書・研究に時間を割いたそうだ。橘はローマ史から組織と訓練の重要性を学び、金融論から統制の必要性を悟ったと伝えられる。そして、農村共同体における「共に生きんとする心」を強調していた橘は、一気に視野を広げて「愛国心」に目覚め、皇道を説くようにもなった。橘は獄中で大きな思想的転換を経験したわけだが、彼の金融に関する見方の変化は注目に値する。
入獄前の橘は、「明治維新は近世ヨーロッパ物質文明の世界的波及と近世資本主義の世界的浸潤に促されて、日本が世界の大勢の渦巻きの中に捲きこまれなくてはならない為になしとげられたる歴史的一変態遂行と看做すことが出来」、「日本資本主義発達上明治政府がなし遂げたる最も特筆すべき大事業は議会政治の輸入よりはむしろ実に貨幣制度の確立に在り」と認識していた。ところが、「資本主義発達に対する貨幣制度と金融機関の発達が如何に重大なる任務を果たしてきたかは周知の事実であって余り説明の要なきものであろう」として、金融のしくみそのものに都市化や農村の困窮を引き起こす原因が内在しているとは考えなかったようなのだ。橘はまた、『農村学』において、具体的な数字を挙げて農家の家計が赤字にあることを示し、農民の窮状を切々と訴えていたのだが、どういうわけでそのような物価体系に組み込まれなければならないのかを踏み込んで考えてはいなかった。
五・一五事件以前の橘は、素朴な感情論で、「資本主義の破農性」を問題にしていたのだ。橘は愛郷塾で農民に複式簿記を教えていたが、入獄前の橘は銀行のバランス・シートについて考察するようなことはなかったわけだ。金融についてヘンリー・フォードは、"People of the nation do not understand our banking / monetary system, for if they did, there would be a revolution"と言い残していたが、獄中で金融論を研究した橘孝三郎は相当なショックを受けたらしく、昭和九年から一〇年にかけての獄中手記に次のような言葉を残している。
「最も注意されなくてはならないのは、社会それ自身の経済的性質である。即ち、富と云うものは本来的に社会的なものであると云う事である。これを考える事なしに、貨幣又は信用と云うことを考へる事は不可能である。」
「調和されたる社会でなければ、調和されたる交換はあり得ない。従ってまた、調和されたる生産分配もあり得ない。次の時代は、何よりも先に貨幣の管理に成功せんことを要求しておる。…交換なき社会はない。社会だといふ事が交換だという事である。」
「信用までが国家が管理統制する必要が、勿論ある。」
「どうしても一切を強力なる国家権力の統制化に持ち来らさねばいけない。でないと皆なまいってしまう。あの有様、この有り様を見る。人間らしい人間があるか。あられない。あられる道理がない。」
獄中で橘孝三郎は、信用創造のしくみが孕んでいる破壊的メカニズムに気づき、農民の自助努力の限界を思い知らされたにちがいない。農民が窮乏する根本的な原因に気づいたはずだ。だが、不幸にも塀の外では、報われない勤労をも厭わぬ皇国農民精神の鍛錬陶冶が活発になっていた。日本の教育史の中では、郷土愛と勤労主義を掲げた農本主義教育がファシズムのイデオロギー形成に寄与したと解釈されてもいるが、郷土愛と勤労主義を説いた当の橘孝三郎は、マネーがいとも簡単に創り出され、それを人々が有り難がることで都市の論理が支えられ、それゆえ郷土愛を育もうにも都市化が進み、農民の勤労は水泡に帰してしまう、ということに気づいたはずだ。
戦後、貧困大衆は経済成長によって一旦救われた。だが、誰もが豊かさの増進を実感できた時代に「土に還れ」との哲学はほとんど顧みられることはなかった。日本の経済力が底上げされたことで、日本列島の環境収容力が上げ底になっていることは忘れられてきた。幸福な時代が続いたが、気がつけば、日本の田舎は無茶苦茶になり、行き過ぎた都市化は歴然としている。そして、いみじくも橘が金融論を学んで直感したように、今や大勢の人々がまいっている。
ところで、マルクス『資本論』の初版は一八六七年、大政奉還と同じ年だ。つまり明治維新以来、次のような予言が、さして気に留められることもなく今日を迎えているわけである。
「ヨーロッパの強制で開かれた日本の外国貿易が、現物地代の貨幣地代への転化という結果をもたらすとすれば、それは、その模範的な農業の破滅となる。その狭い経済的存立条件は解消されるであろう。」(マルクス『資本論(一)』岩波文庫版p.243)
一方、「都市化」「工業化」といった、近代以降の人類の歩みを特徴づけてきた化石燃料の生産は頭打ちである。世界エネルギー機関(IEA)も最近、「世界エネルギーアウトルック二〇一〇」の中で、在来型石油の生産は二〇〇六年がピークだったと認めている。
要するに、田舎は貨幣経済的に割を食う状況に置かれたままで、一方、都市はその存続に不可欠なエネルギー基盤を損なう運命にある。困ったことに、たとえ未来を見据えたとしても、貨幣経済の現実が軛となって行く手が阻まれてしまい、やきもきするしかないのが実情である。なるほど「石油ピークは食料ピーク」という標語は正しいが、その標語を声高に叫ぶだけで金融のしくみが改まるわけでもなく、「リ・ローカライゼーション」が約束の地に至る定石だと早合点すべきではない。橘孝三郎の失敗から教訓を引き出すならば、時宜を得て、いかなる止揚を導けるのか、それが当面の課題である。
・参考文献
橘孝三郎『農村学・前篇』(建設社)
斉藤之男『日本農本主義研究』(農山漁村文化協会)
松沢哲成『橘孝三郎 日本ファシズム原始回帰論派』(三一書房)
保阪正康『五・一五事件 橘孝三郎と愛郷塾の軌跡』(草思社)